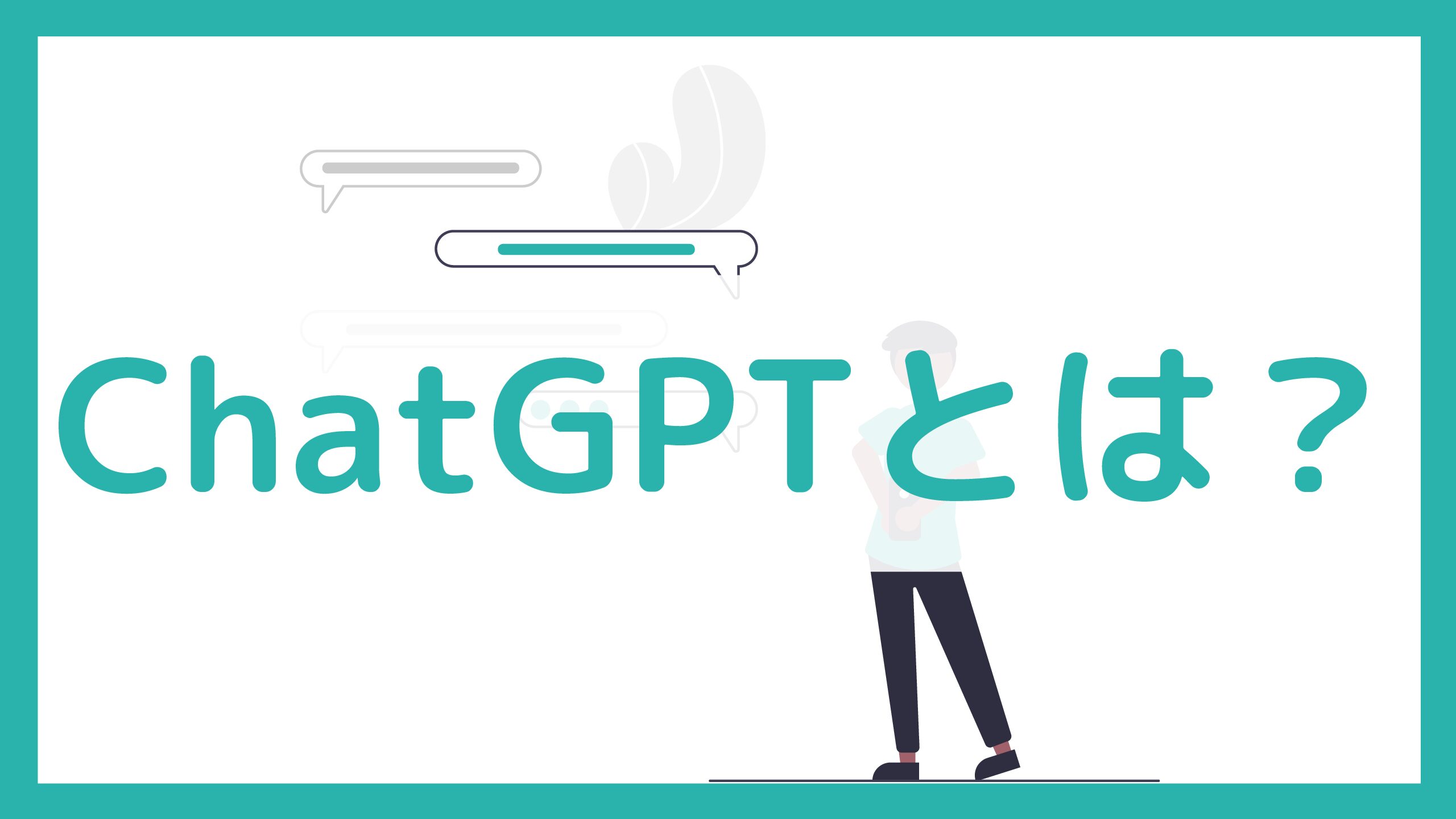手順書通りなのに環境が揃わない、毎回changedになる、機密情報やCI/CDが不安――Ansibleを始めたい人ほど直面する壁は多いもの。
この記事は、最短の準備からPlaybook設計、インベントリとスケール設計、AWX活用、トラブル解決までを実務の型で解説します。
この記事は以下のような人におすすめ!
- Ansibleとは何か知りたい人
- Ansible と Ansible-core の違いが知りたい
- 機密情報やCI/CDが不安な人
Ansibleとは何か
Ansibleは、サーバやネットワーク機器、クラウド、コンテナなどを一括して自動化するためのオープンソースツールです。
構成管理、アプリケーションのデプロイ、そして環境全体のオーケストレーションを、人が読みやすいYAML(Ansible Playbook)で記述できます。
つまり、複雑な運用を「手順書」から「実行可能なコード」に変えることで、手作業のばらつきやヒューマンエラーを減らし、再現性の高い運用を実現します。
1-1. Ansibleでできること(構成管理・デプロイ・オーケストレーションの全体像)
1-1-1. 構成管理の自動化
Ansibleは「所望の状態」を宣言的に記述し、パッケージ・サービス・ファイルを意図した状態に揃えます。
したがって、同じPlaybookを複数回流しても結果は変わらない(冪等)点が強みです。
例として、以下のような日常作業を自動化できます。
- パッケージのインストール/更新
- 設定ファイルの配布と権限設定
- サービスの起動、再起動、ステータス統一
- ユーザーやグループの作成
1-1-2. アプリケーションデプロイ
Ansibleはアプリのビルド、配布、設定、サービス起動までを一気通貫で流せます。
例えば、ローリングデプロイでダウンタイムを抑えたり、複数階層(Web/AP/DB)の更新順序を保証したりできます。
その結果、手順の抜け漏れを防ぎ、安定したリリースを継続できます。
1-1-3. オーケストレーション(環境横断の連携)
複数サーバや複数クラウドにまたがる作業を一連のワークフローとして記述し、順序や依存関係を制御できます。
なぜなら、インベントリ(対象一覧)とグループ変数、そして条件分岐・ハンドラを組み合わせることで、環境差分や例外ケースにも対応できるからです。
1-1-4. 対象領域の広さ(クラウド・ネットワーク・コンテナ)
Ansibleはモジュールとコレクションを通じ、AWSやAzureなどのクラウド、Ciscoなどのネットワーク機器、さらにはDockerやPodmanの操作まで幅広く扱えます。
つまり、運用の自動化を一つの言語(YAML)で統一しやすいのです。
1-2. 仕組みの基礎(エージェントレス、SSH/WinRM、モジュール実行の流れ)
1-2-1. エージェントレスとは
Ansibleはターゲット側に常駐エージェントを入れません。コントロールノードから都度モジュール(小さな実行単位)を配布し、処理して結果を回収します。
だから、導入が軽く、既存環境に影響を与えにくいのが特徴です。
1-2-2. 接続方式(SSHとWinRM)
LinuxやUnix系は主にSSH、WindowsはWinRMで接続します。必要に応じて特権昇格(become)を使い、root権限相当の操作も安全に実行可能です。
1-2-3. モジュール実行の流れ
一般的な流れは次の通りです。
- インベントリで対象ホストを特定
- 事前情報(facts)を収集
- タスクごとに該当モジュールを転送・実行
- 結果(JSON)を回収し、状態変化を記録
- 必要に応じてハンドラでサービス再起動や次工程へ連携
この仕組みにより、Ansibleは「現在の状態」を理解したうえで、安全に変更を適用します。
1-2-4. インベントリと変数管理
静的ファイルや動的インベントリ(クラウドAPI連携)で対象を管理できます。
グループ変数・ホスト変数を使えば、環境ごと(開発・検証・本番)や役割ごと(web、db)に設定を切り替えられます。
1-2-5. PlaybookとRole(再利用の基本)
Ansible PlaybookはYAMLでタスクの順序と条件を記述します。
さらにRoleへ分割すればディレクトリ構成が定まり、テンプレート、ファイル、ハンドラ、タスクが整理され、再利用性が高まります。
Ansible GalaxyやCollectionsを使えば、社内外の知見を簡単に取り込めます。
1-3. 他ツールとの比較(Terraform・Puppet・Chef・Saltの違い)
1-3-1. 目的と実行モデルの違い(早見表)
| ツール | 主目的(得意分野) | 実行モデル | エージェント有無 | 記述スタイル | 向く場面の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansible | 構成管理・デプロイ・オーケストレーション | プッシュ型 | なし(エージェントレス) | YAML(Playbook) | 手早い自動化、混在環境 |
| Terraform | インフラのプロビジョニング(作成・変更) | プラン+適用(宣言的) | なし | HCL(宣言的) | VPCやVM、マネージドサービスの作成 |
| Puppet | 継続的な状態維持(構成管理) | プル型(常駐) | あり | DSL(宣言的) | 大規模で厳密なコンプライアンス |
| Chef | 構成管理・デプロイ | プル型(常駐) | あり | Ruby DSL(手続き寄り) | ルビー文化圏、柔軟なレシピ |
| Salt(SaltStack) | 構成管理・イベント駆動 | プル/プッシュ両対応 | あり/なし(salt-ssh) | YAML(Jinja併用) | 高頻度イベントや即時反応 |
1-3-2. TerraformとAnsibleの関係
Terraformは「基盤を作る」のが得意で、Ansibleは「中身を整える」のが得意です。
したがって、Terraformでネットワークやサーバ資源を用意し、その後にAnsibleでOS設定やアプリ配布を行う併用が実践的です。
1-3-3. Puppet/ChefとAnsibleの違い
PuppetやChefはエージェント常駐のプル型で、継続的な状態維持やドリフト検知を得意とします。
一方、Ansibleはプッシュ型で導入が軽く、アドホックな変更や段階的展開に強みがあります。
つまり、長期的なコンプライアンス重視ならPuppet/Chef、素早い自動化や混在環境ならAnsibleが選びやすいと言えます。
1-3-4. SaltとAnsibleの違い
Saltはイベントドリブンな自動化や即時性に強みがあり、大量ノードへの一斉配布が高速です。
対してAnsibleは学習コストが比較的低く、コミュニティとモジュールの裾野が広いのが利点です。
用途やチームのスキルに合わせて選択しましょう。
1-4. 向いているケース/向かないケースの判断基準
1-4-1. Ansibleが向いているケース
- エージェントを入れにくいセキュリティ要件の環境
- 複数OS・クラウド・ネットワーク機器が混在する環境
- 手順書ベースの運用をYAML化して標準化したい場合
- CI/CDパイプラインに組み込み、デプロイを安定化したい場合
- インシデント対応やアドホック作業を安全に繰り返したい場合
- Ansible Vaultで秘匿情報(パスワード・鍵)を安全に扱いたい場合
1-4-2. Ansibleが向かない/注意が必要なケース
- 常時エージェントによる厳密なドリフト監視・強制が必要な場合(Puppet等が適合)
- サーバ台数が非常に多く、秒単位の即応・イベント駆動が必須な場合(Salt等を検討)
- ほぼすべてがコンテナ/Kubernetesで、宣言的に完結している場合(KubernetesやHelmで統一)
- 超大規模なインフラ作成・変更の計画性(依存関係管理)が主目的の場合(Terraformが適合)
1-4-3. 判断チェックリスト(簡易)
- 変更は「ときどきまとめて」か、「常時監視して即時修正」か
- 異種環境(OS・クラウド・機器)の横断が多いか
- 手順書の属人化を解消したいか
- 学習しやすさ・導入しやすさを優先したいか
- 既存のCI/CDや秘密情報管理と統合しやすいか
1-4-4. 導入時のベストプラクティス
- まずは小さなPlaybookから開始し、Role化して再利用性を高める
- 変数・テンプレート・条件分岐を活用し、環境差分を一本化
- Lintやテスト(Molecule等)で品質を継続的に検証
- Ansible Collections/Galaxyを活用して標準モジュールを優先
- インベントリはグルーピングと命名規約を徹底
- 秘密情報はAnsible Vaultで暗号化し、リポジトリは権限分離
- 実行ログと変更履歴を記録し、ロールバック方針を明確化
最短で始める準備と基本用語
Ansibleを最短で使い始めるために、まずは「入れる・つなぐ・動かす」の三拍子を押さえましょう。
つまり、動作要件を満たしインストールし、基本用語を理解し、最小のYAMLとディレクトリで形を作り、最後にad-hocコマンドで「できる」体験を積みます。
したがって、本章は実務でそのまま使える最短ルートに絞って解説します。
2-1. 動作要件とインストール(Linux/Mac/Windowsのポイント)
2-1-1. 事前要件(最短チェックリスト)
- 制御ノード:Ansibleを実行する端末(Linux/macOS/WSLを推奨)
- 管理対象(Linux系):Python 3系がほぼ必須(raw等の例外を除く)
- 管理対象(Windows):Pythonは不要。WinRM(PowerShell)で接続
- 通信要件:Linux系はSSH、WindowsはWinRMが到達可能であること
- 資格情報:SSH鍵(推奨)またはパスワード。Windowsは管理者権限の資格情報
2-1-2. OS別の入れ方(要点早見表)
| 環境 | 推奨インストール | コマンド例のイメージ | 補足 |
|---|---|---|---|
| Linux(Debian/Ubuntu) | パッケージ or pip | aptでansibleまたはansible-core | なるべく最新が必要ならpip/仮想環境を検討 |
| Linux(RHEL/Fedora系) | dnfでansible-core | sudo dnf install ansible-core | 追加のCollectionsは後から入れる |
| macOS | Homebrew | brew install ansible | すぐ使いたい人向け。Python仮想環境も可 |
| Windows(制御) | WSLでLinux化 | WSL上でLinux手順を実施 | だからWindowsでもUnix系と同様の体験に |
| Windows(管理対象) | 事前にWinRM有効化 | Inventoryでconnection=winrm | ドメイン/証明書方針に合わせて設定 |
ポイントは、まず制御ノードをLinux/macOS(またはWSL)に寄せること。
なぜなら、Ansibleのエコシステムと相性が良く、トラブルシュートが楽だからです。
2-1-3. すぐ使えるインストール例
- Linux(例:Ubuntu)
sudo apt update sudo apt install -y ansible ansible --version
- Fedora/RHEL系(例:Fedora)
sudo dnf install -y ansible-core ansible --version
- macOS(Homebrew)
brew update brew install ansible ansible --version
- Python仮想環境での導入(どのOSでも再現性が高い)
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate # Windowsは .venv\Scripts\activate pip install --upgrade pip pip install ansible-core # 追加機能が多いmetaパッケージは 'ansible'
2-1-4. Windows管理対象の準備(最短の考え方)
- WinRMを有効化(組織ポリシーに合わせたスクリプトを適用)
- インベントリで接続方式を指定
[windows] win01 ansible_host=192.0.2.10 [windows:vars] ansible_connection=winrm ansible_user=Administrator ansible_password=<安全な方法で管理> ansible_port=5986 ansible_winrm_server_cert_validation=ignore # 検証用。商用は適切な証明書で
2-1-5. バージョン管理の考え方(ansible-core と collections)
ansible-core:エンジン+基本モジュール。軽量で読み替えが少ないansible:多数のCollectionを同梱。手早く広範囲を触りたいときに便利
その結果、チームで統一する場合はrequirements.ymlでCollectionsを固定し、仮想環境で隔離するのが安全です。
2-2. 基本用語:制御ノード・管理対象・インベントリ・モジュール・タスク
2-2-1. 制御ノード(Control Node)
Ansibleコマンドを実行する端末のことです。ここにPlaybookやインベントリ、設定ファイルを置き、SSH/WinRM越しに管理対象へ指示を送ります。
2-2-2. 管理対象(Managed Node)
設定を適用されるサーバやネットワーク機器です。LinuxではPythonが、WindowsではPowerShell/WinRMが要となります。つまり、常駐エージェントは不要です。
2-2-3. インベントリ(Inventory)
対象ホストの一覧と属性を定義します。INI風/YAMLのどちらでも記述でき、グループ化や変数割り当てが可能です。したがって、環境(dev/stg/prod)や役割(web/db)ごとに整理できます。
2-2-4. モジュール(Module)
各タスクで呼び出される最小実行単位です。packageやservice、copy、user、Windowsならwin_*系など、目的別に用意されています。
2-2-5. タスク(Task)とハンドラ(Handler)
タスクは「やること」の列挙、ハンドラは状態が変わったときだけ呼ばれる「後処理」(例:サービス再起動)です。この仕組みにより、Ansibleは冪等で安全に変更します。
2-2-6. Play と Playbook
Playは「どのホストに何をするか」のひとまとまり。PlaybookはそれらをYAMLで記述したファイル群です。つまり、運用手順をコード化した“実行可能な手順書”です。
2-2-7. 変数・テンプレート・Facts
- 変数:
group_vars/host_varsやvarsで値を切り替え - テンプレート:Jinja2で設定ファイルを動的生成
- Facts:対象ホストから収集した情報(OS種別、IP、メモリ等)
2-3. YAML基礎とプロジェクト構成(ディレクトリの型)
2-3-1. YAMLの最小ルール(Ansibleで困らないために)
- インデントは半角スペース(推奨2または4)。タブは使わない
- 配列は
-、辞書はkey: valueで表現 - 文字列にコロンや特殊文字が入る場合はクォートで明示
- だから、まずは整形ルールをチームで統一すると事故が減ります
2-3-2. 最小のPlaybook例(Linuxへパッケージ導入)
# site.yml
– name: Install and start nginx
hosts: web
become: true
tasks:
– name: Ensure nginx is present
ansible.builtin.package:
name: nginx
state: present
– name: Ensure nginx is running
ansible.builtin.service:
name: nginx
state: started
enabled: true
2-3-3. インベントリ例(INI と YAML)
- INI風
[web] web01 ansible_host=192.0.2.21 web02 ansible_host=192.0.2.22
- YAML
all: children: web: hosts: web01: { ansible_host: 192.0.2.21 } web02: { ansible_host: 192.0.2.22 }
2-3-4. 推奨ディレクトリ(小規模〜中規模の型)
project/
├─ site.yml
├─ inventories/
│ ├─ dev/hosts
│ └─ prod/hosts
├─ group_vars/
│ ├─ all.yml
│ └─ web.yml
├─ host_vars/
│ └─ web01.yml
├─ roles/
│ └─ webserver/
│ ├─ tasks/main.yml
│ ├─ templates/
│ ├─ files/
│ ├─ handlers/main.yml
│ └─ defaults/main.yml
└─ ansible.cfg
roles/に機能単位で分割し再利用性アップansible.cfgでプロジェクトローカル設定を固定
2-3-5. ansible.cfg(最初に効く最小設定)
[defaults]
inventory = ./inventories/dev/hosts
forks = 20
retry_files_enabled = False
stdout_callback = yaml
[privilege_escalation]
become = True
become_method = sudo
開発初期は簡潔に。なぜなら、設定が少ないほど原因切り分けが容易だからです。
2-4. 初めての実行:ad-hocコマンドで「できる」を体感
2-4-1. 疎通確認(LinuxとWindows)
- Linux系
ansible all -i inventories/dev/hosts -m ansible.builtin.ping
- Windows系
ansible windows -i inventories/dev/hosts -m ansible.windows.win_ping
2-4-2. よく使うad-hoc(パッケージ/サービス/ファイル)
- パッケージ導入(OS差を吸収する
package)
ansible web -i inventories/dev/hosts -b \ -m ansible.builtin.package -a "name=curl state=present"
- サービス起動・自動起動
ansible web -i inventories/dev/hosts -b \ -m ansible.builtin.service -a "name=nginx state=started enabled=true"
- 設定ファイル配布
ansible web -i inventories/dev/hosts -b \ -m ansible.builtin.copy -a "src=./files/index.html dest=/var/www/html/index.html mode=0644"
2-4-3. 失敗しないための実行オプション
--check:変更せずに差分だけ確認(ドライラン)--diff:設定ファイルの差分を表示-K:sudoパスワードを都度入力(必要なときだけ)--limit web01:特定ホストに限定して安全に試行
つまり、まずは小さく当ててから全体へ広げるのが定石です。
2-4-4. 次の一歩:ad-hocからPlaybookへ
ad-hocで効果を確認できたら、同じ操作をPlaybook化してロールへ分割します。
その結果、レビューしやすく再現性も高まり、Ansibleをチームの標準運用に組み込みやすくなります。必要に応じて、ansible-galaxy initでRoleの骨格を自動生成し、requirements.ymlでCollectionsを固定しましょう。
Playbookの書き方・設計指針
Ansible Playbookは「人間が読める運用手順」を「安全に繰り返せるコード」に変える設計が肝心です。
つまり、冪等(同じPlaybookを何度流しても同じ状態に収束)を第一原則に、変数とテンプレートで差分を吸収し、条件分岐とループで重複を排除、さらにハンドラーやタグで再実行を速くします。
したがって、本章では実務でそのまま使えるAnsibleの設計指針を、例と型で整理します。
3-1. タスクとモジュールの基本(idempotent思考)
3-1-1. 冪等(idempotent)とは何か
Ansibleは多くのモジュールが状態を宣言的に扱います(present、absent、startedなど)。
だから、同じPlaybookを再実行しても不要な変更が起きません。
加えて、--check(ドライラン)や--diffを組み合わせれば、変更前に安全に確認できます。
– name: nginxをインストールし起動状態にする
hosts: web
become: true
tasks:
– name: nginxを導入
ansible.builtin.package:
name: nginx
state: present
– name: nginxを起動し自動起動
ansible.builtin.service:
name: nginx
state: started
enabled: true
3-1-2. 典型パターンとアンチパターン(早見表)
| ゴール | 推奨モジュール/手法 | 例 | アンチパターン |
|---|---|---|---|
| パッケージを入れる | package | state: present | shell: apt install ... の手書き |
| 設定ファイル配布 | template/copy | validateで構文検証 | 上書きだけして再起動を忘れる |
| 一度きりの初期化 | command + creates | 目印ファイルで再実行防止 | 無条件でcommandを毎回実行 |
| 外部資材の展開 | unarchive | createsで再展開防止 | 都度展開して毎回changed |
– name: スキーマ初期化(済なら実行しない)
ansible.builtin.command: /usr/local/bin/initdb
args:
creates: /var/lib/myapp/.initialized
3-1-3. 変更検知と失敗判定の制御
registerで結果を受け取り、changed_whenやfailed_whenで厳密に制御します。
つまり、モジュールが提供する冪等だけで足りない場合の保険です。
name: ip_forward値を確認(読み取りのみ)
ansible.builtin.shell: “sysctl -n net.ipv4.ip_forward”
register: ipf
changed_when: false
– name: 値が0なら設定を更新
ansible.builtin.lineinfile:
path: /etc/sysctl.conf
regexp: ‘^net.ipv4.ip_forward=’
line: ‘net.ipv4.ip_forward=1’
when: ipf.stdout | int == 0
notify: sysctl-apply
3-2. 変数・テンプレート(Jinja2)・ファイル配布
3-2-1. 変数の設計(最小ルール)
Ansibleの変数優先順位は複雑ですが、実務では次の簡略ルールで十分です。
なぜなら、役割(Role)を中心に据えると衝突が起きにくいからです。
- 既定値は
roles/<role>/defaults/main.ymlに置く - 環境差分は
group_vars/host_varsで上書き - 一時的な切り替えは
--extra-varsで明示 - 重要値は
ansible-vaultで暗号化
3-2-2. テンプレート(Jinja2)の基本
templateで設定ファイルを生成し、可能ならvalidateで構文検証、notifyで必要時のみ再起動します。
したがって、誤配布や無駄な再起動を防げます。
# tasks/main.yml
– name: nginx.confを配布(構文検証付き)
ansible.builtin.template:
src: templates/nginx.conf.j2
dest: /etc/nginx/nginx.conf
owner: root
group: root
mode: ‘0644’
validate: ‘nginx -t -c %s’
notify: restart nginx
tags: [conf]
# templates/nginx.conf.j2(抜粋)
user {{ nginx_user | default(‘nginx’) }};
worker_processes {{ (ansible_facts.processor_vcpus | default(1)) | int }};
http {
server_tokens {{ nginx_server_tokens | default(‘off’) }};
{% for s in nginx_sites %}
server {
listen {{ s.port }};
server_name {{ s.server_name }};
root {{ s.root }};
}
{% endfor %}
}
3-2-3. ファイル配布と機密情報の扱い
- 静的ファイルは
copy、ディレクトリ作成はfile - 大きな断片は
assembleで連結し、レビュー性を上げる - 機密はVaultに格納し、テンプレート内で参照
# vars/vault.yml(Vaultで暗号化)
db_password: supersecret
# tasks/main.yml
– name: アプリ設定
ansible.builtin.template:
src: app.ini.j2
dest: /etc/myapp/app.ini
vars_files:
– vars/vault.yml
3-3. 条件分岐・ループ・when/withの実践
3-3-1. OS差分の吸収(when)
ディストリビューションごとの分岐はfactsで一元化します。
だから、Playbookを一つに保ったまま複数OSへ配布できます。
– name: 依存パッケージを導入
ansible.builtin.package:
name: “{{ item }}”
state: present
loop: “{{ (ansible_facts.os_family == ‘Debian’) | ternary([‘debhelper’], [‘libselinux-python’]) }}”
3-3-2. ループの型(loop/withの使い分け)
今はloopが標準です。
複雑な入れ子はsubelementsやdict2itemsフィルタでシンプルにします。
# 単純なリスト
– name: パッケージ一括導入
ansible.builtin.package:
name: “{{ item }}”
state: present
loop: “{{ common_packages }}”
# 辞書のループ
– name: ユーザー作成
ansible.builtin.user:
name: “{{ item.key }}”
groups: “{{ item.value.groups }}”
state: present
loop: “{{ users | dict2items }}”
# 親子データ(サイトとエイリアス)
– name: サーバブロック生成
ansible.builtin.template:
src: vhost.conf.j2
dest: “/etc/nginx/conf.d/{{ item.0.name }}.conf”
loop: “{{ sites | subelements(‘aliases’, skip_missing=True) }}”
3-3-3. registerで結果に応じた分岐
実行結果に応じて次の処理を変えます。
したがって、外部コマンドやAPI連携でも安全に組み立てられます。
– name: バージョンを取得
ansible.builtin.command: myapp –version
register: ver
changed_when: false
– name: 旧バージョンならアップグレード
ansible.builtin.import_tasks: tasks/upgrade.yml
when: ver.stdout is version(‘3.2.0’, ‘<‘)
3-4. ハンドラー・通知・タグ運用で再実行を速くする
3-4-1. ハンドラーとnotify/listenの基本
設定が変わったときだけ後処理を実行します。
つまり、無駄な再起動を避けられます。
# tasks
– name: 設定変更時のみ再起動を通知
ansible.builtin.template:
src: app.service.j2
dest: /etc/systemd/system/app.service
notify: restart app
# handlers
– name: restart app
listen: restart app
ansible.builtin.service:
name: app
state: restarted
必要に応じて特定タイミングで即時反映するなら、次のようにします。
– name: ハンドラーをここで処理
ansible.builtin.meta: flush_handlers
3-4-2. タグ設計で部分実行を高速化
タグは再実行時間を縮める強力なスイッチです。
したがって、役割ごと・機能ごとに粒度を決めます。
- 基本タグ案:
pkg(パッケージ)conf(設定)svc(サービス)deploy(配布)db(データベース) - 実行例:
--tags conf,svc、あるいは--skip-tags db - 明示実行専用タスクには
tags: [never, migrate]+--tags migrate
– name: DBマイグレーション(明示時のみ)
ansible.builtin.command: myapp migrate
tags: [never, migrate]
3-4-3. 差分最小化のテクニック
- 事前に
statで変更要否を判定してからcopy - バックアップが必要なら
backup: yes - 読み取りだけのタスクは
changed_when: false - 展開系は
createsで再実行を抑制 - 大規模配布は
serialやthrottleで段階展開
– name: 既存ファイルのハッシュ確認
ansible.builtin.stat:
path: /etc/myapp/app.ini
register: st
– name: 必要なときだけ差し替え
ansible.builtin.copy:
src: files/app.ini
dest: /etc/myapp/app.ini
when: not st.stat.exists or st.stat.checksum != lookup(‘file’, ‘files/app.ini’, errors=’ignore’) | checksum
3-5. 役割分割(Roles)とAnsible Galaxyの使い方
3-5-1. Roleで分ける基準とディレクトリ型
Roleは「関心ごとの分離」です。
つまり、アプリ、DB、Web、監視など機能単位で分けます。
roles/
└─ webserver/
├─ tasks/main.yml
├─ handlers/main.yml
├─ templates/
├─ files/
├─ defaults/main.yml # 変更されうる既定値
├─ vars/main.yml # 固定値(やむを得ず)
└─ meta/main.yml # 依存Role
3-5-2. 依存関係と変数の流儀
- 依存Roleは
meta/main.ymlで宣言(例:geerlingguy.repo-epelなど) - 調整可能な値は
defaults、固定したい値はvarsへ - 取り込みは
import_role(静的)かinclude_role(動的)を使い分け
– name: Webロールを静的に取り込み
ansible.builtin.import_role:
name: webserver
vars:
nginx_server_tokens: “off”
3-5-3. Ansible GalaxyとCollectionsの導入
既製のRoleやCollectionを活用すると、工数を大きく削減できます。
その結果、社内は「自作するより組み合わせる」文化に寄せられます。
# requirements.yml
roles:
– src: geerlingguy.nginx
version: 0.21.3
collections:
– name: community.general
version: “>=8.0.0,<9.0.0”
# 取得・更新(例)
# ansible-galaxy role install -r requirements.yml
# ansible-galaxy collection install -r requirements.yml
Playbook側でCollectionを宣言すれば、接頭辞省略や可読性向上に役立ちます。
– name: Web層セットアップ
hosts: web
collections:
– community.general
roles:
– role: geerlingguy.nginx
実務で効く運用ノウハウ
Ansibleを現場投入する際は、セキュリティと再現性、そしてスピードの三点を同時に満たす設計が要です。
つまり、機密情報は厳格に守り、テストを自動化し、インベントリと接続方式を正しく選び、OSや機器特性を踏まえた運用に落とし込むことが重要です。
したがって、本章では「すぐ真似できる型」に絞って解説します。
4-1. 機密情報の守り方(Ansible Vaultの使いどころ)
4-1-1. 何をVaultで暗号化すべきか
- パスワード、APIトークン、SSH秘密鍵、証明書の秘密鍵
- データベース接続情報、クラウドのアクセスキー
- 本番固有の設定値(内部ホスト名、監視用コミュニティ文字列 など)
一方、暗号化しない方がよいものは次の通りです。なぜなら、レビュー性と差分追跡を落とすからです。
- 一般設定(ポート番号、タイムアウトなど機微でない値)
- 大容量ファイル(バイナリ)や頻繁に変わるログ設定
4-1-2. Vaultの基本運用(チームで破綻しない型)
- ファイル単位で暗号化:
group_vars/prod/vault.ymlのように環境別に分離 - 一行だけ暗号化:
ansible-vault encrypt_stringを使い、Playbookへ直接埋め込む - パスワード配布:
ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILEを使い、CIではシークレット変数から投入 - レビュー性確保:機密以外は平文の
defaults/group_varsに残す
4-1-3. 失敗しない読み込み順序
# site.yml
– hosts: app
vars_files:
– group_vars/common.yml
– group_vars/{{ env }}/vault.yml # 最後に読み込む
roles:
– app
最後にVaultを読み込むと、環境ごとの差分が意図通りに上書きされます。
だから、変数の衝突が減ります。
4-2. テスト(Molecule)とCI/CD連携(GitHub Actions/GitLab)
4-2-1. Moleculeの最小シナリオ
- ドライバ:Docker/Podmanを選択(速い・使い捨て・再現性)
- シナリオ:
create→converge→verify→destroy - 検証:pytest + testinfra で「ポートが開いているか」「サービスが起動しているか」をチェック
# 例:Role直下で
molecule init scenario -r webserver -d docker
molecule test
4-2-2. GitHub Actionsでの定番パイプライン
- 依存取得:
ansible-galaxy install -r requirements.yml - 静的検査:
ansible-lint、yamllint、ansible-playbook --syntax-check - ユニット相当:
molecule test(シナリオごとに並列) - デプロイ前検証:対象外部へは
--check --diffでプルリク時に乾式実行
# .github/workflows/ci.yml(抜粋)
name: ansible-ci
on: [push, pull_request]
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
– uses: actions/checkout@v4
– uses: actions/setup-python@v5
with: { python-version: ‘3.11’ }
– run: pip install ansible-core ansible-lint molecule[docker] pytest testinfra
– run: ansible-galaxy install -r requirements.yml
– run: ansible-lint
– run: ansible-playbook -i inventories/ci/hosts site.yml –syntax-check
– run: molecule test –all
4-2-3. GitLab CIでのシンプル構成
# .gitlab-ci.yml(抜粋)
image: python:3.11
services: [docker:dind]
stages: [lint, test]
before_script:
– pip install ansible-core ansible-lint molecule[docker] pytest testinfra
– ansible-galaxy install -r requirements.yml
lint:
stage: lint
script:
– ansible-lint
test:
stage: test
script:
– molecule test –all
CI上のVaultパスワードはランナーのシークレットに保存し、ジョブ中にファイルへ書き出して使用します。
したがって、履歴に残さず安全です。
4-3. インベントリ設計(グループ化・動的インベントリ・クラウド連携)
4-3-1. グルーピングの基本指針
- 層で分ける:
web、app、db - 環境で分ける:
dev、stg、prod - 組み合わせは子グループで表現:
[prod:children] web_prod app_prod - 変数は「広い→狭い」の順に上書き:
group_vars/all→group_vars/web→host_vars/web01
4-3-2. 静的と動的のハイブリッド
- 変動しにくいオンプレは静的ファイル
- クラウドは動的インベントリプラグイン(例:
aws_ec2、azure_rm、gcp_compute) - タグ駆動でグループ化し、ローリング更新の
serial対象を自動抽出
# aws_ec2動的インベントリ(抜粋)
plugin: amazon.aws.aws_ec2
regions: [“ap-northeast-1”]
filters:
tag:Role: “web”
keyed_groups:
– key: tags.Env
prefix: “”
compose:
ansible_host: public_ip_address
4-3-3. 接続と性能のベース設定
# ansible.cfg(抜粋)
[defaults]
forks = 50
timeout = 30
gathering = smart
fact_caching = jsonfile
fact_caching_connection = .facts
host_key_checking = False
[ssh_connection]
pipelining = True
ssh_args = -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=15m
pipeliningやコネクション再利用を有効化すると、並列数を抑えつつ高速化できます。
だから、大規模配布でもトラフィック過多になりにくいのです.
4-4. Windowsとネットワーク機器の自動化の勘所
4-4-1. Windowsの要点(WinRM・権限・モジュール)
- 接続は
ansible_connection=winrm、既定は5986/TLS。証明書運用かドメイン連携を前提に - 権限昇格はLinuxの
becomeと異なるため、実行ユーザーを適切に設計 - ソフト配布は
ansible.windows.win_package、設定はwin_regedit、再起動はwin_reboot - パッケージ管理は
community.windows.chocolateyの活用が便利 - 改行コードやパス区切り(
\)の違いをテンプレートで吸収
[windows]
win01 ansible_host=203.0.113.10
[windows:vars]
ansible_connection=winrm
ansible_user=Administrator
ansible_password={{ vault_win_password }}
ansible_winrm_transport=credssp
ansible_winrm_server_cert_validation=validate
4-4-2. ネットワーク機器の要点(ベンダープラグイン・差分管理)
- 接続は
network_cliやhttpapi、OSはansible_network_os=ios|nxos|junosなどを明示 *-config系モジュールで意図状態を投入し、backup: yesとdiffを活用gather_facts: noを忘れずに。代わりにansible_net_*facts を参照- 段階展開:
serialで少数ずつ適用し、失敗時にロールバック
– hosts: switches
connection: network_cli
gather_facts: no
tasks:
– name: intended configを適用
cisco.ios.ios_config:
src: templates/ios_intended.cfg.j2
backup: yes
4-5. ベストプラクティスとやりがちな落とし穴
4-5-1. ベストプラクティス要点
- 冪等を最優先:
state指定、creates、changed_whenで補強 - テンプレートは
validateとnotifyを併用して安全に再起動 - タグ設計:
pkg、conf、svc、deployなどで部分実行を高速化 - 品質ゲート:
ansible-lint、--syntax-check、Molecule の三点セット - 性能:
pipelining、fact caching、strategy: free、不要時はgather_facts: false - ログと追跡:
-vvvでの一時デバッグと、実行履歴の保存(CIログ・Artifactory等)
4-5-2. よくある落とし穴と回避策(早見表)
| 落とし穴 | 何が起きるか | 回避策 |
|---|---|---|
shell/commandを多用 | 冪等性が失われる | まず対応モジュールを探す。やむを得ず使うときはcreatesやunless相当を設計 |
latest指定の乱用 | 意図せず更新が走る | バージョン固定。更新はメンテナンスタグで明示的に |
| Vaultに全て入れる | レビュー不能になる | 機密だけをVault化。構造化された平文を保つ |
| 変数の多重上書き | デバッグ困難 | defaults→group_vars→host_varsの階層を厳守。ansible-playbook -eは最小限 |
| 動的インベントリ無設定 | 予期せぬ対象に配布 | タグ基準で抽出し、--limitやserialで段階適用 |
| Windows/Linuxの思考混同 | 実行失敗や権限エラー | 各OS専用モジュールを選択し、接続方式・権限モデルを分けて設計 |
| 大量同時変更 | サービス断や輻輳 | serial、throttle、max_fail_percentageで安全弁を設置 |
4-5-3. 運用チェックリスト(配布前に見る)
- 変更はドライラン済みか(
--check --diff) - 重要変更にタグが付いているか(部分実行できるか)
- ロールの
defaultsが現実的な初期値になっているか rebootやserviceの通知条件が正しいか- CIでMoleculeが緑になっているか
- Vaultパスワードの取り扱いが組織ポリシーに沿っているか
スケールさせる導入設計
Ansibleをチームや全社規模で運用するときに重要なのは、スケールさせるための「型」を最初から用意しておくことです。
つまり、小さく始めて共通テンプレートを固め、段階的に並列度やコントローラを増やし、パフォーマンスとセキュリティを両立させます。
したがって本章では、Ansibleを中長期で拡張するための設計指針を、テンプレート、チューニング、運用統制の観点で整理します。
5-1. 小規模〜中規模の標準構成例(テンプレート一式)
5-1-1. リポジトリの標準ディレクトリ(そのまま使える型)
ansible-repo/
├─ site.yml # 入口Playbook(役割の束ね)
├─ inventories/
│ ├─ dev/hosts # 環境ごとのインベントリ
│ ├─ stg/hosts
│ └─ prod/hosts
├─ group_vars/
│ ├─ all.yml # 全体既定
│ ├─ web.yml # 役割別
│ └─ prod.yml # 環境別(機微はVaultへ)
├─ host_vars/
│ └─ web01.yml
├─ roles/
│ ├─ webserver/ # 機能単位のRole
│ └─ app/
├─ files/ # 小さめの静的配布物
├─ templates/ # Jinja2テンプレート
├─ vars/
│ └─ vault.yml # ansible-vaultで暗号化
├─ collections/
│ └─ requirements.yml # 利用するCollections固定
├─ molecule/
│ └─ default/ # 最低限の検証シナリオ
└─ ansible.cfg # プロジェクトローカル設定
この「型」をチームで共有すると、レビューが揃い、Ansibleの学習コストも下がります。
つまり、スケールの原点は“同じ型で書く”ことです。
5-1-2. ansible.cfg の最小チューニング
[defaults]
inventory = ./inventories/dev/hosts
forks = 25
timeout = 30
gathering = smart
fact_caching = jsonfile
fact_caching_connection = .facts
retry_files_enabled = False
stdout_callback = yaml
callback_whitelist = profile_tasks,timer
[ssh_connection]
pipelining = True
ssh_args = -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=15m -o ServerAliveInterval=30
pipeliningとコネクション再利用で往復を減らし、profile_tasksで遅いタスクを可視化します。
したがって、早い段階から性能のボトルネックを特定できます。
5-1-3. 実行設計の基本ルール
- 変更系タスクにタグ付け(
pkg,conf,svc,deploy) - 読み取りタスクは
changed_when: false - 長時間処理は
asyncとpollで非同期実行 - 段階展開は
serial: 20%のように割合指定 - 重要タスクは
--check --diffで事前確認
このルールは小規模でも効きますが、中規模化したときの事故を大幅に減らします。
5-2. 大規模化のポイント(並列度、コントローラ分割、AWX/Automation Platform活用)
5-2-1. 並列度の考え方(forksだけに頼らない)
forksは接続数上限。むやみに増やすとネットワークとターゲットに負荷serialでロールアウト幅を制御し、max_fail_percentageで停止条件を設定throttle(タスク単位の同時数制限)で重い処理を抑制strategy: freeでホスト間の待ち合わせを減らす(順序依存が無いとき)
5-2-2. コントローラ分割(論理と物理のレイヤ)
- 論理分割:環境(dev/stg/prod)、ドメイン(Web/DB/ネットワーク)、地域(APAC/EMEA)
- 物理解:複数の制御ノードを用意し、ジョブ種別でキューを分離
- SCMリポジトリは単一でも、実行は「プロジェクト別・キュー別」に分ける
つまり、運用負荷の平準化と影響範囲の限定が同時に達成できます。
5-2-3. AWX / Ansible Automation Platform の活用
- ジョブテンプレートで「誰でも同じ実行」を保証(変数はSurveyで入力)
- RBACでインベントリ・資格情報・テンプレートを分離し最小権限で運用
- 実行環境(Execution Environment)で依存パッケージをコンテナ化し再現性を担保
- スケジューラで定時作業やコンプライアンスチェックを自動化
- プライベートハブ(Collections/ロールの社内配布)で依存のバージョンと品質を統制
この仕組みにより、Ansibleの“人依存”を排し、監査性を高められます。
5-3. パフォーマンス最適化(forks・strategy・キャッシュ)
5-3-1. 早見表:ボトルネック別の対策
| 症状 | 主因 | 対策 |
|---|---|---|
| 接続確立が遅い | SSHハンドシェイク、DNS | ControlPersist、pipelining、名前解決キャッシュ、踏み台の近接配置 |
| タスクが足踏み | ホスト間の待ち合わせ | strategy: free、タスク分割、run_once+delegate_to |
| 冪等でも毎回changed | モジュールの使い方 | creates, unless相当やchanged_whenの明示、適切なモジュール選択 |
| facts収集が重い | gather_factsデフォルト | gather_facts: false、gather_subset: min、factキャッシュ |
| I/Oが遅い | テンプレート大量配布 | 圧縮転送、差分配布、asyncで分散 |
5-3-2. Playbook側の具体テクニック
– hosts: web
strategy: free
serial: 25%
gather_facts: false
vars:
ansible_ssh_common_args: “-o ControlMaster=auto -o ControlPersist=15m”
pre_tasks:
– name: 必要なfactsだけを軽量収集
ansible.builtin.setup:
gather_subset:
– network
– virtual
tasks:
– name: 重いコンパイル処理は非同期
ansible.builtin.command: make build
async: 1800
poll: 0
throttle: 5
5-3-3. キャッシュの使い分け
- factsは
jsonfileキャッシュで再利用(短時間の再実行に有効) - Artifact(ログ・結果)はCIやAWXで保存期間を決めて保管
- 重い外部API呼び出しは
set_factで当該Play内キャッシュ
結果として、リラン時の時間が大幅に短縮されます。
5-3-4. 遅いタスクの特定と継続改善
callback_whitelist = profile_tasks,timerで実行時間を可視化ansible-lintでアンチパターンを検出- 変更頻度の高いRoleから優先的に最適化
継続的にメトリクスを取り、遅い順に潰すのが最短です。
5-4. セキュリティとコンプライアンス(権限・監査・変更履歴)
5-4-1. 最小権限の原則(Ansible × RBAC)
- 実行者はAWX/Automation Platformのロールで権限最小化
- 資格情報は「種類ごと」に分離(SSH、クラウド、ネットワーク、Vault)
- Playbook側でも
becomeの使用範囲を最小化し、昇格は必要タスクに限定 - コントロールノードの鍵はホスト別に分け、横展開を防止
5-4-2. 機密情報の扱い(Vaultと外部KMS)
- 機密は
ansible-vaultで暗号化し、平文の構造は維持 - 外部KMSやシークレットマネージャ(例:HSM, Vault製品)連携の検討
- CI/CDではシークレットをランナーの安全なストアから注入
だから、「人が見えず、機械だけが使える」流れを徹底できます。
5-4-3. 監査・変更履歴(誰が・いつ・何を)
- SCMのコミットIDをジョブへ埋め込み、実行ログと突合
- AWXのジョブイベント、出力、差分を長期保管(期間と閲覧権限を定義)
- 重要テンプレートは
--check --diffを必須化し、承認フローを設置 - サーバ側にも監査ログ(sudoログ、変更検知)を併用
この多層の記録により、インシデント時の時系列再現が容易になります。
5-4-4. コンプライアンス自動化の型
- テクニカルコントロールをPlaybook化(CIS準拠などをRole化)
- 定期スキャンをスケジューラで回し、逸脱はチケット起票へ連携
- 本番適用前にポリシー検査(
ansible-lintルールや社内ガイドライン) - 監査証跡は「計画(PR)→実行(Job)→結果(レポート)」で一元化
その結果、Ansibleが「守りの自動化」の要になります。

IT資格を取りたいけど、何から始めたらいいか分からない方へ
「この講座を使えば、合格に一気に近づけます。」
- 出題傾向に絞ったカリキュラム
- 講師に質問できて、挫折しない
- 学びながら就職サポートも受けられる
独学よりも、確実で早い。
まずは無料で相談してみませんか?