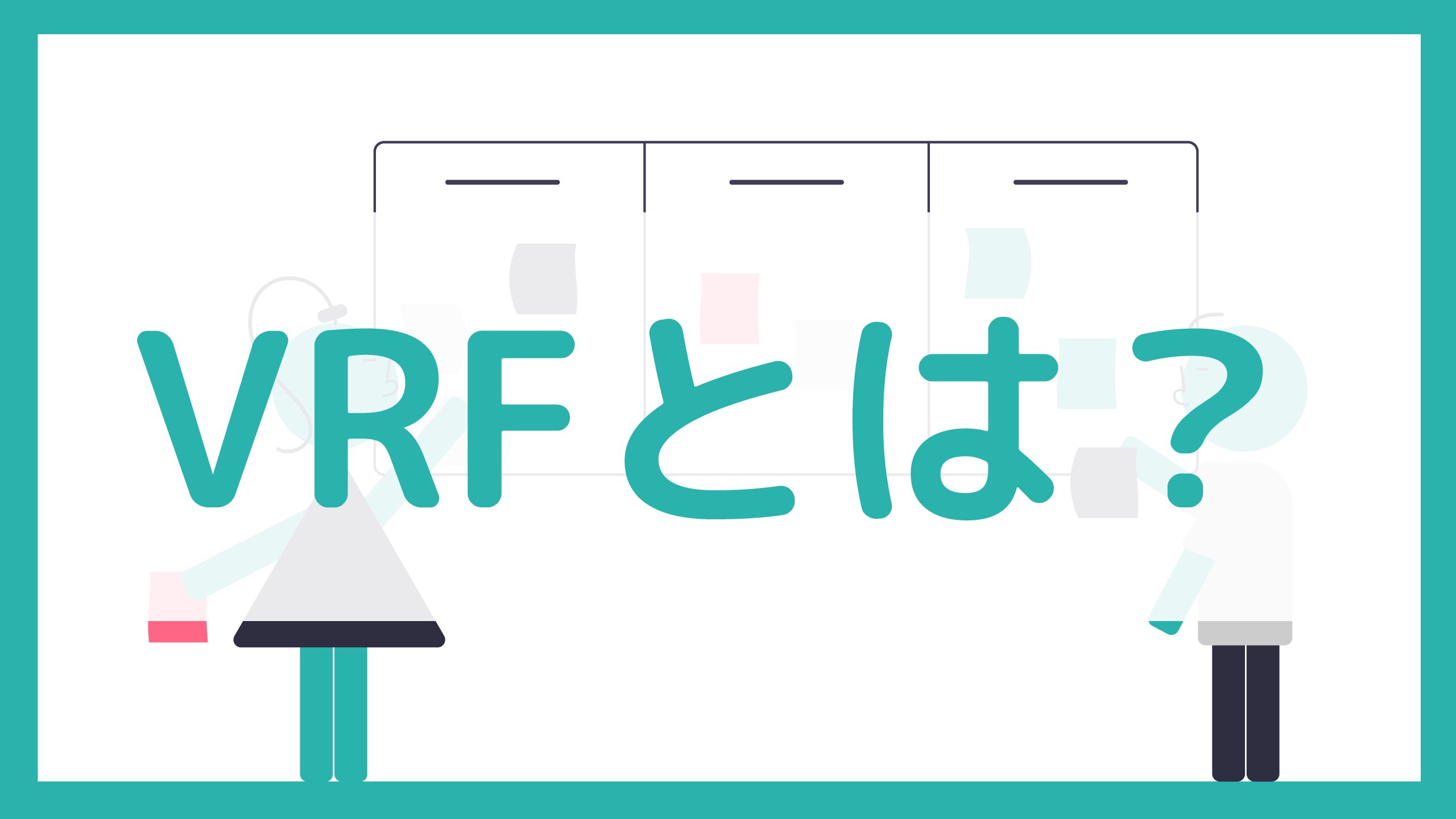社内ネットワークを見直そうとすると、必ずと言っていいほど登場するのが「L3スイッチ」です。
しかし、L2スイッチやルーターとの違い、本当に自社に必要なのか、どの機種を選べばよいのか分からず悩んでいませんか。
本記事では、L3スイッチの基礎から仕組み、具体的な使いどころ、選定・設計・運用のポイント、さらにトラブル事例までを、ネットワーク初心者の方にも分かりやすく整理して解説します。
この記事は以下のような人におすすめ!
- L3スイッチとは何か知りたい人
- L2スイッチ・L3スイッチ・ルーターの違いが分からず困惑している人
- L3スイッチの選定時にどのような基準で選べばよいのか知りたい人
目次
L3スイッチの基礎知識
L3スイッチ(レイヤ3スイッチ)は、「スイッチ」と「ルーター」の中間のような役割を持つネットワーク機器です。
この記事のこのパートでは、次の3点を押さえることで、L3スイッチの基礎をしっかり理解できるようにします。
- L3スイッチとは何か
- なぜL3スイッチが必要になったのか(背景と役割)
- OSI参照モデルのどこに位置づけられるのか
順番に見ていきましょう。
1-1. L3スイッチとは何か?
L3スイッチとは、「L2スイッチ(レイヤ2スイッチ)の機能」に「ルーター(レイヤ3)の機能」を組み合わせたネットワーク機器です。
つまり、L3スイッチは次の2つを同時にこなします。
- 同じネットワーク(同じセグメント)内の通信を中継する
- 異なるネットワーク同士(異なるセグメント同士)の通信を中継する(ルーティング)
少しイメージしやすくするために、L2スイッチ・ルーター・L3スイッチを簡単に比較してみます。
| 機器 | 主な役割 | 動作する層 | 代表的な機能 |
|---|---|---|---|
| L2スイッチ | 同一ネットワーク内での転送 | レイヤ2(データリンク) | MACアドレス学習、VLAN |
| ルーター | 異なるネットワーク間の転送 | レイヤ3(ネットワーク) | IPルーティング、NAT |
| L3スイッチ | スイッチング+ルーティングを高速に実行 | 主にレイヤ3+レイヤ2 | VLAN間ルーティング、スタティック/動的ルーティング |
このように、L3スイッチは「VLANでネットワークを分けたいが、その間の通信も高速に行いたい」といったニーズに応えるための機器です。
なぜなら、通常のルーターだけで同じことを行うと、どうしてもスループットや遅延がネックになりやすいからです。
L3スイッチの代表的な機能には、次のようなものがあります。
- VLAN間ルーティング(インターネットワーク内のセグメント間通信)
- スタティックルート、OSPFなどのダイナミックルーティング
- ACL(アクセスリスト)による簡易的なフィルタリング
- ループ防止や冗長化のためのプロトコルサポート(機種による)
したがって、「社内LANをVLANで分割しつつ、部署間の通信は高速にしたい」「フロアごとにネットワークを分けたい」といった要件があるとき、L3スイッチは非常に有力な選択肢になります。
1-2. L3スイッチが登場した背景と役割
次に、「そもそもなぜL3スイッチが登場したのか」を整理します。
背景を知ると、L3スイッチをどんな場面で使うべきかが理解しやすくなります。
1-2-1. 従来の課題
かつては、社内ネットワークの構成はおおむね次のような形でした。
- 各フロアや部署ごとにL2スイッチを配置
- セグメント間の通信はルーターに集約
- ルーターが全てのVLAN間通信を担当
この構成には、次のような課題がありました。
- ルーターに負荷が集中し、トラフィックが増えると性能が頭打ちになる
- ネットワーク分割(VLAN増加)に伴い、ルーターの設定・構成が複雑になる
- 高性能なルーターほど価格が高く、コスト面でも負担が大きい
つまり、「ネットワークをどんどん細かく分割したいが、ルーターに負荷もコストも集中してしまう」というジレンマがあったわけです。
1-2-2. L3スイッチが解決したこと
この課題を解決するために登場したのがL3スイッチです。
L3スイッチは、スイッチ内部でルーティング処理をハードウェア的に高速に行えるため、次のようなメリットがあります。
- VLAN間通信をスイッチ内で処理することで、従来のルーターより高速に転送できる
- コア側にL3スイッチを配置することで、トラフィックを分散させられる
- 機種によってはルーターよりもコストパフォーマンスに優れる
結果として、L3スイッチは次のような役割を担うことが増えました。
- 社内LANの「コアスイッチ」として、全体の通信を集約・制御する
- 部署間・フロア間の「VLAN間ルーティング」を担当する
- 一部のルーティング機能を肩代わりして、ルーターの負荷を軽減する
このように、L3スイッチは「ネットワークを柔軟に分割しながら、高速で安定した通信を実現するための中核機器」として使われるようになりました。
1-3. OSI参照モデルで捉えるL3スイッチの位置づけ
最後に、OSI参照モデルの視点からL3スイッチを整理しておきましょう。
なぜなら、OSIモデルで考えると「どこまでがL3スイッチの役割で、どこから先は別の機器の役割なのか」が明確になるからです。
1-3-1. OSI参照モデルと代表的な機器
まずは、OSI参照モデルのうちL3スイッチと関係の深い層だけを抜粋して表にします。
| OSI層 | 層の名前 | 主な役割 | 代表的な機器・機能 |
|---|---|---|---|
| レイヤ1 | 物理層 | 電気信号・光信号の送受信 | ケーブル、ハブなど |
| レイヤ2 | データリンク層 | 同一ネットワーク内のフレーム転送 | L2スイッチ、MACアドレス |
| レイヤ3 | ネットワーク層 | 異なるネットワーク間の転送 | ルーター、IPアドレス、経路制御 |
L3スイッチは名前の通り「レイヤ3(ネットワーク層)」の機能を持ちますが、同時にレイヤ2のスイッチング機能も備えています。
つまり、L3スイッチは「レイヤ2とレイヤ3の両方をカバーする機器」と言えます。
1-3-2. L3スイッチの位置づけ
OSI参照モデルで見たときのL3スイッチのイメージは、次のようになります。
- レイヤ2として
- MACアドレスを学習してフレームを転送
- VLANでネットワークを論理的に分割
- レイヤ3として
- IPアドレスに基づいてパケットを転送(ルーティング)
- VLANごとにIPネットワークを割り当て、VLAN間の通信を制御
このように、L3スイッチは「レイヤ2の世界」と「レイヤ3の世界」を橋渡しする存在です。
だからこそ、L3スイッチを理解するときには次のポイントを意識すると整理しやすくなります。
- 同じVLAN内の通信 → L2スイッチとして働く
- 異なるVLAN間の通信 → L3スイッチとして働く(ルーティング)
L3スイッチと他機器との違い
ここからは、「L3スイッチと他のネットワーク機器は何が違うのか」「どの機器をどの場面で使うべきか」という疑問を整理していきます。
特に、L2スイッチ・ルーター・ファイアウォールとの違いを理解しておくと、ネットワーク設計や機器選定で迷いにくくなります。
2-1. L2スイッチとL3スイッチの違い
まずは、もっとも混同されやすい「L2スイッチ」と「L3スイッチ」の違いから整理します。
どちらも「スイッチ」と呼ばれますが、できることには明確な差があります。
2-1-1. L2スイッチとL3スイッチの役割の違い
L2スイッチとL3スイッチの役割を一言でまとめると、次のようになります。
- L2スイッチ
同じネットワーク内での通信を効率よくさばく機器 - L3スイッチ
同じネットワーク内の通信に加えて、異なるネットワーク間の通信(VLAN間通信)もさばける機器
表で比較するとイメージしやすくなります。
| 項目 | L2スイッチ | L3スイッチ |
|---|---|---|
| 主な役割 | 同一セグメント内のフレーム転送 | VLAN間ルーティング+同一セグメント内のフレーム転送 |
| 使用する情報 | MACアドレス | IPアドレス+MACアドレス |
| OSI参照モデル | レイヤ2 | レイヤ2+レイヤ3 |
| VLAN間通信 | 不可(ルーターが必要) | 可能(L3スイッチ内で完結) |
| 主な利用シーン | エッジスイッチ、単純なフロアスイッチ | コアスイッチ、ディストリビューション層、VLAN間の中継 |
つまり、L2スイッチは「同じネットワークの中だけをつなぐイメージ」で、L3スイッチは「ネットワークとネットワークをつなぐ機能も持つスイッチ」と捉えると分かりやすいです。
2-1-2. L3スイッチが処理する情報の違い
次に「何を見て転送しているか」という視点で比較してみましょう。
- L2スイッチ
フレームの宛先MACアドレスを見て、どのポートに出すかを決めます。
そのため、MACアドレステーブルを使って転送します。 - L3スイッチ
IPパケットの宛先IPアドレスを見て、どのネットワークに転送するかを判断します。
その際、ルーティングテーブル(経路情報)を使います。
したがって、L3スイッチは「MACアドレス」と「IPアドレス」の両方を扱えるという点で、L2スイッチよりも一段上の制御が可能になります。
2-1-3. L2スイッチとL3スイッチの使い分け
では、実際のネットワークではL2スイッチとL3スイッチをどのように使い分けるのでしょうか。
よくあるパターンは次の通りです。
- フロアごとの端末接続用 → L2スイッチ
- 拠点全体のVLAN間通信を担う中核 → L3スイッチ
使い分けのイメージを箇条書きで整理すると、次のようになります。
- 端末がたくさんぶら下がる「末端側」はL2スイッチ
- ネットワークの中心でVLANをまたいで通信をさばくのはL3スイッチ
- VLANを使わず、単純なネットワークだけならL2スイッチで十分な場合もある
- しかし、部署ごとやシステムごとにネットワークを分けたい場合、L3スイッチが重要になる
つまり、「ネットワークを分割してセキュリティと運用性を高めながら、社内の通信は高速にしたい」という要件があるなら、L3スイッチの導入を前提に考えるのが自然です。
2-2. ルーターとL3スイッチの使い分け
次に、多くの人が悩む「ルーターとL3スイッチの違い」と「どちらを使えばよいか」というテーマです。
どちらもIPアドレスを使ってルーティングを行いますが、得意分野が異なります。
2-2-1. ルーターとL3スイッチの共通点
まず、共通点を整理します。
ルーターもL3スイッチも、次のような機能を持っています。
- IPアドレスに基づくパケット転送(ルーティング)
- スタティックルートの設定
- 一部のルーティングプロトコル(OSPFなど)への対応
- VLAN間通信の制御(構成次第)
そのため、「L3スイッチがあればルーターはいらないのでは?」と感じる方もいます。
しかし、実際には役割が異なることが多く、両方を併用するネットワーク構成が一般的です。
2-2-2. ルーターとL3スイッチの違い(性能・機能・コスト)
次に、ルーターとL3スイッチの違いを整理します。
| 観点 | ルーター | L3スイッチ |
|---|---|---|
| 得意な領域 | 拠点間接続、WAN、インターネット接続 | LAN内部、VLAN間通信、社内トラフィックの高速処理 |
| 機能の傾向 | NAT、VPN、詳細なルーティング、QoSなど豊富 | VLAN間ルーティング、高速転送が中心 |
| 性能 | 機種によるが、L3スイッチほどポート数は多くない | 多ポート+高速スイッチングに強い |
| 配置場所の例 | インターネット回線の出口、拠点間VPN | 社内LANのコア、ディストリビューション層 |
したがって、L3スイッチは「社内LANの中を高速にルーティングする担当」、ルーターは「社内LANと外部ネットワーク(インターネットや他拠点)をつなぐ担当」と考えると分かりやすいです。
2-2-3. シーン別に見るL3スイッチとルーターの使い分け
具体的なシーン別に、どのようにL3スイッチとルーターを使い分けるかを例示します。
- 企業LANの構成
- コア:L3スイッチ(VLAN間ルーティングを担当)
- エッジ:L2スイッチ(端末接続用)
- インターネット出口:ルーター(NATやファイアウォール連携)
- 拠点間VPNを張る場合
- 拠点側:ルーターがVPN終端を担当
- 拠点内LAN:L3スイッチが社内のVLAN間ルーティングを担当
- 小規模オフィスでネットワークが単純な場合
- インターネット接続用のブロードバンドルーター+L2スイッチだけでも運用可能
- ただし、将来の拡張(VLAN導入など)を見据えるなら、早めにL3スイッチを導入しておくと拡張しやすい
このように、「LAN内部のトラフィックをどうさばくか」はL3スイッチ、「拠点間やインターネットとのやり取りをどう制御するか」はルーター、という役割分担で考えると、機器選定がスムーズになります。
2-3. L3スイッチ vs その他ネットワーク機器(ファイアウォール等)
最後に、L3スイッチとファイアウォールなどのセキュリティ機器との違いを整理します。
なぜなら、L3スイッチにも簡易的なフィルタリング機能があるため、「L3スイッチだけでセキュリティも任せてよいのか?」と疑問に思う人が多いからです。
2-3-1. L3スイッチとファイアウォールの違い
L3スイッチとファイアウォールは、そもそも設計思想が異なります。
- L3スイッチ
- 目的:ネットワーク内の通信を高速かつ効率的に転送すること
- 機能:ルーティング、VLAN間通信、簡易ACLによるフィルタリングなど
- ファイアウォール
- 目的:不要な通信や不正な通信を遮断し、ネットワークを保護すること
- 機能:ステートフルインスペクション、アプリケーション制御、詳細なポリシー設定など
つまり、L3スイッチは「転送」が主役で、ファイアウォールは「防御」が主役です。
L3スイッチにもACLによる制御はありますが、細かいセキュリティポリシーを組むには限界があります。
2-3-2. L3スイッチとUTM/次世代ファイアウォールとの関係
近年では、UTM(統合脅威管理)や次世代ファイアウォールなど、高度なセキュリティ機能を持つ機器が一般的になっています。
これらとL3スイッチの関係性も押さえておきましょう。
- L3スイッチ
- 社内LAN内部のトラフィックを高速にルーティング
- VLAN間の通信制御もある程度可能
- UTM/次世代ファイアウォール
- インターネットアクセス時のWebフィルタリング、アプリケーション制御、IPS/IDSなどを担当
- 社内から外への通信だけでなく、社内セグメント間の通信も詳細に監査・制御可能
このように、L3スイッチは「トラフィックをさばく高速道路」、UTMやファイアウォールは「料金所や検問所」のようなイメージで考えると、役割の違いが分かりやすくなります。
2-3-3. どこまでL3スイッチに任せてよいか
では、「どこまでL3スイッチに任せてよくて、どこから先は専用のセキュリティ機器に任せるべきか」を整理します。
L3スイッチに任せやすい領域の例
- VLAN間の基本的な通信制御
- 一部のIPアドレスやポートの制限(簡易ACL)
- 管理ネットワークやサーバネットワークへの最低限のアクセス制御
専用のファイアウォールやUTMに任せるべき領域の例
- インターネットとの境界防御(入口・出口対策)
- 詳細なユーザー単位のアクセス制御やログ管理
- マルウェア対策、アプリケーション制御、IPS/IDSなどの高度なセキュリティ機能
- ゼロトラストやセグメンテーションを前提とした細かなポリシー適用
したがって、「L3スイッチさえあればセキュリティ機器はいらない」と考えるのは危険です。
L3スイッチはあくまで「ネットワークを高速・柔軟に構成するための機器」であり、セキュリティについてはファイアウォールやUTMなどと組み合わせて設計することが重要です。
このように、L3スイッチはL2スイッチやルーター、ファイアウォールなどと役割を分担しながら使うことで、性能・コスト・セキュリティのバランスが取れたネットワークを実現できます。
L3スイッチの仕組み・動作解説
ここまでで、L3スイッチが「スイッチとルーターの機能を併せ持つ機器」であることを見てきました。
ここでは一歩進んで、
- L3スイッチで具体的に何ができるのか
- L3スイッチ内部でどのような処理が行われているのか
- 実際のネットワーク構成の中でL3スイッチがどう動くのか
という「仕組み」と「動作」の視点から、L3スイッチをもう少し深く理解していきます。
3-1. L3スイッチで何ができるか?(ルーティング・VLAN間通信)
まずは、L3スイッチが現場でどのような役割を果たしているのかを整理します。
L3スイッチというキーワードを聞いたとき、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「VLAN間ルーティング」です。
しかし、それ以外にもL3スイッチならではの機能がいくつかあります。
3-1-1. L3スイッチの代表的な機能
L3スイッチでできることを、ざっくり一覧にすると次のようになります。
| 機能カテゴリ | L3スイッチでできることの例 |
|---|---|
| VLAN・セグメント | VLANの作成・管理、VLAN間ルーティング |
| ルーティング | スタティックルート、ダイナミックルーティング(OSPFなど) |
| フィルタリング | ACLによる通信制御(IP/ポート単位の許可・拒否) |
| 冗長化・信頼性 | ルーティングプロトコルによる経路冗長、スイッチ間冗長 |
| 運用・管理 | SNMP、ログ取得、監視連携など |
つまり、L3スイッチは「社内ネットワークの中核」として、単なるスイッチ以上の多様な役割を担うことができます。
3-1-2. L3スイッチによるVLAN間通信(インタVLANルーティング)
L3スイッチのキーフレーズとも言えるのが「VLAN間通信」です。
例えば、次のような構成を考えてみます。
- VLAN 10:総務部(192.168.10.0/24)
- VLAN 20:営業部(192.168.20.0/24)
- VLAN 30:サーバ(192.168.30.0/24)
このとき、各VLANのPC同士は同じVLAN内なら直接通信できますが、VLANをまたいだ通信は通常そのままでは届きません。
ここで登場するのがL3スイッチです。
L3スイッチは、各VLANに対して「デフォルトゲートウェイ」となるIPアドレスを持ち、VLAN間のルーティングを行います。
例)
- VLAN 10 のゲートウェイ:192.168.10.1(L3スイッチ)
- VLAN 20 のゲートウェイ:192.168.20.1(L3スイッチ)
- VLAN 30 のゲートウェイ:192.168.30.1(L3スイッチ)
このように設定すると、
- 総務部PC → 営業部PC
- 営業部PC → サーバ用ネットワーク
といった通信も、L3スイッチが間に入り、IPアドレスを見て適切なVLANへ転送してくれます。
つまり、L3スイッチは「複数のVLANをまたいだ社内LANのハブ」のような役割を果たしていると言えます。
3-1-3. L3スイッチによるルーティングの種類
L3スイッチが行うルーティングには、いくつか種類があります。
代表的なものを挙げると次のとおりです。
- スタティックルーティング
管理者が手動でルート(経路)を設定する方式。
小〜中規模ネットワーク、経路が固定的なネットワークに向いています。 - ダイナミックルーティング
OSPFなどのルーティングプロトコルを使い、L3スイッチ同士やルーターと経路情報を自動交換する方式。
経路が複雑なネットワークや、冗長構成を組む場合に便利です。 - デフォルトルート
「このネットワークの外へ出る通信は全部ここへ」という一本の大まかな出口を決める設定。
多くの場合、L3スイッチからインターネット用ルーターへ向けてデフォルトルートを設定します。
したがって、L3スイッチは単にVLAN間の通信をつなぐだけでなく、ネットワーク全体の経路設計においても重要な役割を担う機器と言えます。
3-2. L3スイッチの内部構造と処理フロー
次に、もう少し技術寄りの視点として、L3スイッチ内部でどのような処理が行われているのかを見ていきます。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、「どの情報を見て、どう判断しているか」という流れが分かれば、L3スイッチの設定やトラブルシュートがぐっと楽になります。
3-2-1. L3スイッチの内部構造(制御プレーンと転送プレーン)
L3スイッチの内部は、大きく次の2つの役割に分かれていると考えると理解しやすいです。
- 制御プレーン(コントロールプレーン)
経路計算や設定の処理を行う頭脳部分。CPUが担当します。
例:ルーティングプロトコル(OSPF)で経路を計算する、管理者の設定を反映する など。 - 転送プレーン(データプレーン)
実際のパケットを高速に転送する部分。専用チップ(ASIC)などが担当します。
例:届いたパケットをテーブルに基づいて即座に転送する処理 など。
つまり、L3スイッチは「CPUで賢く考えた結果(ルーティングテーブルなど)を、専用ハードウェアに流し込んで、高速に転送している」と言えます。
3-2-2. L3スイッチが持つ主なテーブル
L3スイッチの内部では、さまざまな「テーブル(表)」が使われています。代表的なものを挙げると以下の通りです。
| テーブル名 | 内容・役割 |
|---|---|
| MACアドレステーブル | MACアドレスとポートの対応表(L2スイッチングに使用) |
| ARPテーブル | IPアドレスとMACアドレスの対応表 |
| ルーティングテーブル | どのネットワークへ行くにはどのインターフェースを使うか |
| FIB(転送情報ベース) | 実際の高速転送で使用される最適化された経路情報 |
簡単に言えば、
- どのMACアドレスがどのポートにいるか(L2情報)
- どのIPネットワークへ行くにはどの経路か(L3情報)
をL3スイッチ内部でしっかり覚えておき、その情報を使って高速に通信をさばいている、というイメージです。
3-2-3. L3スイッチの処理フロー(L2 → L3 → L2)
それでは、L3スイッチを経由する通信が、実際にはどのような流れで処理されるのでしょうか。
VLAN 10 のPCから、VLAN 20 のサーバへ通信するケースを例に説明します。
処理の流れを大まかにすると、次の通りです。
- 端末がデフォルトゲートウェイ(L3スイッチのIP)へパケットを送る
- 送信元PCは、宛先が別ネットワークであることを認識し、L3スイッチのIPアドレス宛にフレームを送ります。
- L3スイッチがフレームを受信
- まずレイヤ2としてフレームを受け取り、どのポートから来たかを把握します。
- L3スイッチがL3処理(ルーティング)を実行
- IPヘッダを見て、宛先IPアドレスを確認します。
- ルーティングテーブルから「このIPはVLAN 20 側へ出すべき」と判断します。
- 宛先VLAN側のMACアドレス解決(ARP)
- L3スイッチは、宛先IPアドレスに対応するMACアドレスをARPテーブルで確認します。
- なければARPリクエストを送って解決します。
- L2フレームとして再カプセル化して転送
- 宛先VLAN(VLAN 20)側のポートから、宛先MAC宛てにフレームを送出します。
このように、L3スイッチの処理は「L2で受ける → L3で判断する → もう一度L2として送り出す」という流れで動いています。
したがって、L3スイッチを理解するうえでは、「L2とL3の役割が機器の中で行ったり来たりしている」というイメージを持っておくと、トラブル時の調査ポイントも見えやすくなります。
3-3. 実際のネットワーク構成でのL3スイッチの動き
最後に、L3スイッチが実際のネットワーク構成の中でどのように動いているかを、具体例で確認していきます。
ここでは「よくある企業ネットワーク」をイメージして解説します。
3-3-1. 典型的なL3スイッチの配置例
よくある構成は、次のような三層構造です。
- コア層:
社内LAN全体の中心となるL3スイッチを配置 - ディストリビューション層:
フロアや部門ごとのL3スイッチ(または高機能L2スイッチ) - アクセス層:
端末やプリンタが接続されるL2スイッチ
シンプルにまとめると、
- アクセス層(L2スイッチ)…端末を収容する
- コア/ディストリビューション層(L3スイッチ)…VLAN間通信やルーティングを担当する
という役割分担です。
3-3-2. VLAN内通信とVLAN間通信でのL3スイッチの動き
ここでは、L3スイッチがどの場面で動くかを、2パターンに分けて整理します。
- 同じVLAN内の通信
- 例:同じ部署のPC同士が通信
- 動き:
- 基本的にはL2スイッチの機能で完結
- L3スイッチが関わらない、もしくはL3機能は使われない
- VLAN間の通信
- 例:営業部PC(VLAN 20)からサーバVLAN(VLAN 30)へのアクセス
- 動き:
- 各端末は自分のVLANのデフォルトゲートウェイ(L3スイッチ)へ通信を送る
- L3スイッチがルーティングを行い、別VLANへ転送
- ここで初めてL3スイッチの「L3機能」が活躍する
つまり、L3スイッチは「VLANをまたぐ通信」が発生したときに、本領を発揮する機器です。
3-3-3. インターネット接続時のL3スイッチの役割
もう一歩踏み込んで、「社内からインターネットへの通信」の流れも見てみましょう。
よくある構成は次のようなイメージです。
- 各フロア:L2スイッチにPCを接続
- 中心:L3スイッチが全VLANを集約
- その先:インターネット接続用ルーターやファイアウォールへ接続
通信の流れは、次のようになります。
- クライアントPCが外部サイト(インターネット上のIP)へアクセス
- PCは自分のデフォルトゲートウェイ(L3スイッチ)へパケットを送信
- L3スイッチは「社内向けではないIP」と判断し、デフォルトルートに従ってルーター/ファイアウォールへ転送
- ルーターがNATなどを行い、インターネットへ通信を出す
このときL3スイッチは、社内各VLANから上がってくるトラフィックを集約し、「外に出すべき通信はルーターへ」「社内向けは別VLANへ」と振り分ける重要な役割を担っています。
したがって、L3スイッチのルーティング設定やVLAN設計に問題があると、インターネットに出られない、特定VLANだけ通信できない、といったトラブルが起きやすくなります。
L3スイッチの仕組みと動作をここまで整理してきましたが、ポイントをまとめると次の通りです。
- L3スイッチは、VLAN間通信やルーティングを高速に処理するための社内LANの中核機器
- 内部では、MACテーブル・ルーティングテーブル・ARPテーブルなどを組み合わせて処理している
- 実際のネットワーク構成では、L3スイッチが「社内の各VLAN」と「インターネットや他拠点」との橋渡し役になる
L3スイッチを使う場面・用途
ここまでで、L3スイッチの機能や仕組みを理解してきました。
では実際に、「どんなネットワークでL3スイッチを使うべきか?」「どんな規模や構成に向いているのか?」を具体的に見ていきましょう。
同時に、導入を避けるべきケースや注意点も整理しておくことで、L3スイッチをより効果的に活用できるようになります。
4-1. どんなネットワークで使うべきか?(企業LAN/VLAN/分散拠点)
L3スイッチは、特定の規模や構成に適した機器です。
特に、「ネットワークを複数のVLANに分けたい」「拠点間通信を高速化したい」といった要件を持つネットワークで威力を発揮します。
4-1-1. 企業LAN環境での利用
企業LANは、L3スイッチがもっとも活躍する典型的な環境です。
理由は、部署ごと・用途ごとにネットワークを分ける必要があるからです。
たとえば、次のような構成が一般的です。
| 部署/用途 | VLAN番号 | IPネットワーク |
|---|---|---|
| 管理部門 | VLAN10 | 192.168.10.0/24 |
| 営業部門 | VLAN20 | 192.168.20.0/24 |
| サーバー群 | VLAN30 | 192.168.30.0/24 |
| 無線LAN/ゲスト | VLAN40 | 192.168.40.0/24 |
このようにVLANで分割された環境では、部署間通信やサーバアクセスのたびにVLAN間通信が発生します。
ここでL3スイッチを導入することで、VLAN間ルーティングをスイッチ内部で高速に処理できるようになります。
その結果、ルーターの負荷を下げ、ネットワーク全体の遅延を減らすことができます。
つまり、L3スイッチは企業LANの中核、いわゆる「コアスイッチ」として最適な選択肢です。
4-1-2. VLANを活用するネットワーク構成での利用
近年、セキュリティ強化や運用効率の観点から、VLANを活用してネットワークを分割するケースが増えています。
L3スイッチは、こうした「セグメント化されたネットワーク」で欠かせない存在です。
VLANを使う目的の一例:
- 部署・部門ごとに通信を分離し、情報漏えいリスクを軽減
- IoT機器・ゲスト用Wi-Fiなどを他ネットワークから隔離
- ブロードキャストドメインを縮小してネットワーク負荷を軽減
ただし、VLANを増やせばその分、VLAN間通信の制御が必要になります。
L2スイッチではこれができないため、L3スイッチを導入することでスムーズに運用できるようになります。
4-1-3. 分散拠点・大規模施設での利用
複数拠点や複数フロアを持つネットワークでも、L3スイッチは効果的です。
なぜなら、拠点間の通信を最適経路で転送し、トラフィックを分散できるからです。
例として、次のような構成を考えます。
- 各フロアや部署ごとにL2スイッチを配置
- 各L2スイッチをL3スイッチに集約(ディストリビューション層)
- L3スイッチがルーティングを担当し、上位のルーターやファイアウォールへ接続
この構成では、社内通信の多くがL3スイッチ内で完結するため、全体の通信遅延が減り、ネットワーク全体が効率化されます。
したがって、複数拠点・複数階層に分かれたLAN環境では、L3スイッチの導入が非常に有効です。
4-2. 小規模環境と大規模環境での適用例
L3スイッチは、企業の規模やネットワーク構成によって、導入目的や設計ポイントが異なります。
ここでは、小規模環境と大規模環境での具体的な適用例を比較しながら解説します。
4-2-1. 小規模環境でのL3スイッチ利用例
小規模オフィスや数十台規模のネットワークでは、「L3スイッチは不要では?」と思われることもあります。
しかし、以下のようなケースではL3スイッチの導入が効果的です。
- 部署ごとにネットワークを分けてセキュリティを確保したい
- 管理ネットワークやゲストWi-Fiを分離したい
- ネットワーク拡張を見据えて、将来的にVLAN構成を取り入れたい
たとえば、小規模な企業が次のような構成を組む場合:
| 用途 | VLAN | IPセグメント |
|---|---|---|
| 社員端末用 | VLAN10 | 192.168.10.0/24 |
| 管理者用 | VLAN20 | 192.168.20.0/24 |
| ゲストWi-Fi | VLAN30 | 192.168.30.0/24 |
この場合、L3スイッチを1台導入すれば、これらのVLAN間通信を効率的に制御できます。
さらに、ネットワークの拡張(新フロアや新システム追加)にも柔軟に対応できます。
つまり、小規模環境でのL3スイッチ導入は、「将来の拡張性」を見据えた投資としても価値があります。
4-2-2. 大規模環境でのL3スイッチ利用例
一方、大規模な企業ネットワークでは、L3スイッチは必須レベルの存在です。
理由は、VLANの数や通信経路が増え、単純なルーターでは処理しきれないからです。
大規模環境におけるL3スイッチの主な役割:
- VLAN間通信を高速に処理(ルーターより低遅延)
- 複数のL3スイッチ間でルーティングプロトコル(OSPFなど)を使用
- ネットワーク冗長化を実現(VRRP・HSRPなど)
- ネットワーク全体のトラフィックを最適化
たとえば、拠点ごとにL3スイッチを配置し、それらをコアスイッチで束ねる構成にすることで、冗長性とスケーラビリティを両立できます。
| 層 | 主な機能 | 機器例 |
|---|---|---|
| コア層 | 拠点間・フロア間の通信集約 | 高性能L3スイッチ |
| ディストリビューション層 | 各フロア・部署の通信分岐 | 中規模L3スイッチ |
| アクセス層 | 端末接続(L2通信中心) | L2スイッチ |
したがって、大規模ネットワークでは、L3スイッチが「通信の最適経路を選択し、ネットワークを支える頭脳」として中心的役割を果たします。
4-3. 導入を避けるべきケース・注意点
L3スイッチは非常に便利な機器ですが、すべての環境に最適というわけではありません。
ここでは、「L3スイッチの導入を避けるべきケース」と「導入時の注意点」を整理しておきます。
4-3-1. L3スイッチ導入を避けた方が良いケース
次のようなケースでは、L3スイッチの導入効果が薄い、またはコストに見合わない可能性があります。
- 単一ネットワークで構成された小規模LAN
例:全端末が同一セグメントで、VLANを利用していない。
→ この場合、L2スイッチで十分。 - インターネット接続専用の単純構成
例:家庭用ルーター+L2スイッチで完結するオフィス。
→ VLAN間通信が不要ならL3機能を活用する機会がない。 - 運用管理リソースが限られている環境
L3スイッチの設定・運用には一定のネットワーク知識が必要。
→ ネットワーク担当者が少ない環境では、管理が負担になる場合もある。
4-3-2. L3スイッチ導入時の注意点
L3スイッチを導入する際には、次の点に注意して設計を進めることが重要です。
| 注意ポイント | 内容 |
|---|---|
| VLAN設計 | VLANを無計画に増やすと運用が複雑化。構成管理ルールを明確にする。 |
| IPアドレス設計 | VLANごとに異なるIPセグメントを割り当て、重複を避ける。 |
| ルーティング設計 | スタティックかダイナミックか、将来の拡張性を考慮して選択する。 |
| セキュリティ対策 | ACL設定だけに頼らず、ファイアウォールやUTMと連携する。 |
| 冗長化 | コアスイッチが単一障害点(SPOF)にならないように冗長構成を採用。 |
また、L3スイッチは高機能である分、機種によってサポートするルーティングプロトコルやACLの種類が異なります。
そのため、導入前に「どの機能が必要か」を明確にし、過不足のないモデルを選定することが大切です。
L3スイッチ選定・設計のチェックポイント
L3スイッチは、単に「性能が高そうだから」という理由だけで選んでしまうと、あとで拡張できなかったり、冗長構成が組めなかったりといった問題が発生しやすい機器です。
つまり、L3スイッチは「選び方」と「設計の仕方」がとても重要なネットワーク機器だと言えます。
ここでは、
- L3スイッチを選定するときの性能・機能要件
- L3スイッチを含むネットワーク設計時に押さえるべき論点
- 導入コストと運用コストを踏まえた計画の立て方
という三つの観点から、具体的なチェックポイントを整理していきます。
5-1. スイッチ選定時の性能・機能要件(ポート数・冗長性・ルーティングプロトコル)
まずは「そもそもどんなL3スイッチを選ぶべきか」という視点です。
L3スイッチは見た目が似ていても、中身の性能や機能は機種ごとに大きく異なります。したがって、以下のポイントを整理しながら選定することが重要です。
5-1-1. 必要なポート数とインタフェース種別を見積もる
最初に考えるべきは、L3スイッチに「何ポート必要なのか」「どの速度のポートが必要なのか」という基本要件です。
なぜなら、ポート数が足りなかったり、速度が不足していると、すぐにボトルネックになってしまうからです。
代表的な観点は次の通りです。
- アクセス用ポート数(1G / 2.5G / 10G など)
- アップリンク用ポート数(10G / 40G / 100G などのSFP/SFP+ポート)
- 将来増設用の空きポート枠(余裕をどれくらい持たせるか)
簡単なチェック表にすると、以下のイメージです。
| 項目 | 今必要な数 | 3年後の想定 | 推奨計画値(今+余裕) |
|---|---|---|---|
| 1Gアクセスポート | 40 | 60 | 48〜64 |
| 10Gアップリンクポート | 2 | 4 | 4〜6 |
| サーバ接続用10G/25Gポート | 4 | 8 | 8〜12 |
このように、「現在必要な分」だけでなく「数年後の拡張」も考慮してL3スイッチのポート数を決めることが重要です。
5-1-2. 冗長性・信頼性(電源・スタック・リンク冗長)
次に、L3スイッチの「止まらない仕組み」をどう用意するかを考えます。
L3スイッチはコアやディストリビューションとして使われることが多いため、ダウンすると社内ネットワーク全体に影響します。
チェックしたい冗長性のポイントは次の通りです。
- 二重化電源に対応しているか
- 電源ユニットの冗長構成が可能か
- スタック構成・クラスタ構成に対応しているか
- 複数台のL3スイッチを論理的に1台として動かせるか
- リンクアグリゲーション(ポートチャネル)対応
- 上位スイッチ/サーバと複数リンク束ねて帯域・冗長性を確保できるか
例えば、「コアL3スイッチなら電源冗長は必須」「ディストリビューションスイッチはスタック対応だと運用が楽になる」といった基準を社内で決めておくと、機種選定がスムーズになります。
5-1-3. ルーティングプロトコル・機能要件の確認
L3スイッチの選定で意外と見落とされがちなのが、「どのルーティングプロトコルに対応しているか」「どこまで高度な機能が必要か」です。
主な確認ポイントは次のとおりです。
- スタティックルートだけで足りるか、それともOSPFなどのダイナミックルーティングが必要か
- VRRP・HSRPなどのゲートウェイ冗長プロトコルが必要か
- ポリシーベースルーティング(特定トラフィックを別経路へ流す)を使う予定があるか
- マルチキャストルーティングなど特殊な要件があるか
つまり、「今できること」だけでなく、「今後やりたいこと」も含めてL3スイッチの機能をチェックしておくと、買い替えのタイミングを先延ばしにできます。
5-2. 設計時に押さえておきたい論点(VLAN設計・冗長構成・拡張性)
次に、L3スイッチを「どう使うか」、つまりネットワーク設計時のポイントです。
L3スイッチ自体がどれだけ高性能でも、設計を誤ると性能を引き出せません。
したがって、設計段階でしっかりと検討しておく必要があります。
5-2-1. VLAN設計の基本方針を決める
L3スイッチを導入する最大の理由の一つが、「VLANでネットワークを分割し、L3スイッチでVLAN間通信を制御する」ことです。
そのため、まずはVLAN設計の方針を明確にしましょう。
VLAN設計の考え方の例:
- 部署単位で分ける(総務・営業・開発・管理など)
- 用途単位で分ける(サーバ、クライアント、ゲストWi-Fi、IoT機器など)
- セキュリティレベルで分ける(重要情報系、一般業務系、検証環境など)
VLAN設計時には、次の点を意識すると整理しやすくなります。
- VLAN数が多すぎると運用が複雑になるため、目的を明確にする
- VLANごとのIPアドレス設計とセットで考える
- L3スイッチ上でのインタフェース(SVI)の数や命名ルールを統一する
このように、最初に「分け方のルール」を決めておくと、L3スイッチの設定もシンプルで管理しやすくなります。
5-2-2. 冗長構成と経路設計をセットで考える
L3スイッチは、多くの場合ネットワークの中核に位置します。
だからこそ、冗長構成と経路設計をセットで考えることが重要です。
代表的な冗長構成の考え方:
- コアL3スイッチを2台構成にして、VRRP/HSRPでゲートウェイを冗長化する
- ディストリビューション層とコア層を、リンクアグリゲーションで多重接続する
- L3スイッチ間でOSPFなどを使い、複数経路を自動的に切り替えられるようにする
経路設計で意識したいこと:
- どの経路が「メイン」で、どの経路が「バックアップ」なのか
- ループが起きないように、レイヤ2とレイヤ3の両方の構成を意識する
- どのL3スイッチがどのネットワークの「デフォルトゲートウェイ」なのかを整理する
つまり、L3スイッチの配置・数・冗長化の方法を決める際には、「故障時にどうトラフィックが切り替わるか」までイメージして設計することが重要です。
5-2-3. 拡張性を見込んだアドレス設計とL3スイッチ構成
ネットワークは一度作って終わりではなく、必ずと言ってよいほど拡張されます。
したがって、L3スイッチの設計時には「数年後の姿」をある程度想定しておくことが大切です。
拡張性を確保するためのポイント:
- IPアドレスは余裕を持ったセグメント設計にする(将来のVLAN追加分も見込む)
- L3スイッチのCPU・メモリ・ルーティングテーブル容量に余裕を持つモデルを選ぶ
- 追加のL3スイッチをスタック参加させたり、上位に増設できる構成にしておく
例えば、最初からギリギリのアドレス設計をしてしまうと、新しい部署追加のたびにアドレス再設計が必要になります。
L3スイッチを長く使い続けるためにも、「拡張前提の設計」を意識しましょう。
5-3. 導入コストと運用コストを考慮した計画
最後に、L3スイッチの導入を現実的な「お金の話」に落とし込んでいきます。
L3スイッチは安い機器ではないため、初期費用だけでなく、運用コスト・保守コストも含めてトータルで判断することが重要です。
5-3-1. 導入コスト(初期費用)の考え方
L3スイッチの導入コストとしては、主に次の要素があります。
- L3スイッチ本体の購入費用
- 電源モジュールやSFPモジュールなどオプションの費用
- 導入時の設定・構築作業費(外部ベンダーに依頼する場合)
ここで重要なのは、「最安モデルを選べばよい」というわけではないことです。
なぜなら、機能が不足していてすぐに買い替えになれば、結果的に高くついてしまうからです。
そのため、次のようなスタンスが理想的です。
- 今すぐ使う機能と、近い将来使う可能性が高い機能は、最初から備えたL3スイッチを選ぶ
- ただし、数年先まで使うか分からない機能に対しては、過剰投資を避ける
つまり、「何でも入りのハイエンド」か「とりあえずのローエンド」かではなく、自社の要件に適したミドルレンジのL3スイッチを選ぶバランス感覚が大切です。
5-3-2. 運用コスト(保守・運用工数)の見積もり
L3スイッチの費用は、購入して終わりではありません。
運用にかかるコストも考慮しておく必要があります。
運用コストの主な内訳:
- 保守サポート契約の費用(ハード保守・ソフトウェアアップデート)
- 障害対応・設定変更などにかかる運用担当者の工数
- 定期的なファームウェアアップデートや設定バックアップの作業時間
ここで意識したいのは、「運用しやすいL3スイッチを選ぶこと」で運用コストを下げられるという点です。
例えば、
- Web GUIやAPIが使いやすく、設定変更や確認が簡単なL3スイッチ
- ログ・監視機能が充実しており、障害切り分けがしやすいL3スイッチ
- 設定テンプレートや自動化ツールとの相性が良いL3スイッチ
こうした観点で機種を選ぶと、運用担当者の負担を大きく減らすことができます。
5-3-3. L3スイッチ投資の費用対効果を評価する
最後に、「L3スイッチの導入によって何が良くなるのか」を明文化しておくことが重要です。
なぜなら、費用対効果が説明できれば、社内の承認も得やすくなるからです。
L3スイッチ導入による代表的な効果:
- VLAN分割とL3スイッチによる制御で、セキュリティと可用性が向上する
- ルーターだけに比べて、社内LANの通信性能が向上し、業務効率が上がる
- 冗長構成により、ネットワーク停止リスクを軽減できる
- 拡張性の高い設計により、将来の増設時の追加コストを抑えられる
これらを、簡単な表に整理しておくと分かりやすくなります。
| 観点 | L3スイッチ導入前 | L3スイッチ導入後 |
|---|---|---|
| 性能 | VLAN間通信がルーターに集中 | L3スイッチ内で高速処理 |
| セキュリティ | 単一セグメントでの運用が多い | VLAN分割+ACLでセグメント制御 |
| 可用性 | 単一機器故障で全体停止のリスク | 冗長構成により障害耐性が向上 |
| 拡張性 | 増設のたびに大規模変更が必要 | 事前設計によりスムーズに拡張可能 |
このように、「L3スイッチ導入で何がどれくらい良くなるのか」を整理しておくと、単なる機器購入ではなく「投資」として説明しやすくなります。
L3スイッチ運用・トラブル対策
ここまでで、L3スイッチの機能・設計・用途を一通り押さえてきました。
しかし、実際の現場では「導入したあと」をどう運用するか、そして「トラブルが起きたときにどう対処するか」が非常に重要です。
つまり、L3スイッチは「入れて終わり」ではなく、「監視・障害予防・トラブル対応」まで含めて設計しておくことで、はじめて本来の力を発揮します。
ここでは、
- L3スイッチの運用監視ポイントと障害予防の考え方
- 実際によく起きるトラブル事例と、そのときの対応方法
を整理していきます。
6-1. L3スイッチの運用監視ポイントと障害予防
L3スイッチの運用では、「どこを見ておけば、異常にすぐ気づけるか」を明確にしておくことが大切です。
なぜなら、異常の“前兆”に気づければ、大きな障害になる前に対処できるからです。
6-1-1. L3スイッチ運用で押さえるべき基本視点
まず、L3スイッチの運用監視を考えるときの基本視点を整理しておきましょう。
L3スイッチを監視するときの代表的な観点は次のとおりです。
- 性能の観点
CPU使用率・メモリ使用率・スループット・遅延など - ハードウェアの観点
ポートのリンク状態・エラーパケット・電源・ファン状態など - 論理構成の観点
VLAN・ルーティングテーブル・ARPテーブル・STP状態など - セキュリティ/変更管理の観点
ACL設定変更、コンフィグ変更履歴、ログ監査など
表にまとめると、L3スイッチの運用で意識したい「何を」「なぜ」見るのかが整理しやすくなります。
| 観点 | 監視対象例 | 見る理由 |
|---|---|---|
| 性能 | CPU・メモリ・トラフィック量 | 負荷増大や異常トラフィックの早期検知のため |
| ハード | ポート状態・エラー・電源・温度 | 故障や物理障害の前兆をつかむため |
| 論理構成 | VLAN・ルート・ARP・STP | 誤設定や経路不整合がないか確認するため |
| セキュリティ | ACL・ログ・コンフィグ変更履歴 | 意図しない設定変更や不審なアクセス検知のため |
したがって、L3スイッチの運用は「単にリンクが上がっているかどうかを見る」だけでは不十分で、上記のような複数の観点から継続的にチェックする必要があります。
6-1-2. 監視すべき代表的な項目
次に、L3スイッチで「具体的にどの項目を監視すべきか」をもう少し細かく見ていきます。
監視に入れておきたい代表項目は、次のようなものです。
- インタフェース(ポート)関連
- 入出力トラフィック量(帯域の逼迫状況)
- エラーパケット数(CRCエラー、衝突、ドロップなど)
- 管理者が意図しないポートアップ(不正接続など)
- CPU/メモリ
- CPU使用率が高止まりしていないか
- メモリ使用率やバッファ使用率が飽和していないか
- ルーティング情報
- スタティックルートの有効性
- ダイナミックルーティング(OSPFなど)のネイバー状態
- ルーティングテーブルの急激な変動の有無
- VLAN/ブリッジ関連
- VLANインタフェース(SVI)のステータス
- STPの状態(ルートブリッジの変動、ブロッキングポートの変化)
- ログ
- 再起動ログ、インタフェースのUp/Downログ
- 設定変更ログ(誰が・いつ・何を変更したか)
ポイントは、「平常時の状態」を把握しておくことです。
そうすれば、普段と違う値(異常なトラフィック増加、一時的なルート変動など)が起きたときに、すぐに気づけます。
6-1-3. 障害を未然に防ぐための日常運用
L3スイッチの障害予防は、監視だけでなく「日常運用」とセットで考えると効果的です。
具体的には、次のような運用ルールを持っておくと、トラブルを大きく減らすことができます。
- コンフィグ管理
- 定期的な設定バックアップ(自動化できるとなお良い)
- バージョン管理(いつどの設定に変わったかを記録)
- 変更管理
- 変更前に必ず設計書や影響範囲を確認する
- 作業手順書を作成し、作業後は結果を記録する
- 変更作業は業務時間外・メンテナンス時間帯に行う
- ファームウェア/OS管理
- ベンダー推奨の安定バージョンを使用する
- 重大な脆弱性・不具合情報が出た場合は、計画的にアップデートする
- 定期点検
- ログの定期確認(重大なWarning/Errorが出ていないか)
- ポートのエラー率やトラフィック傾向の定期レビュー
- 冗長構成のフェイルオーバーテスト(年に一度でも実施すると安心)
つまり、「L3スイッチに何かあったら調べる」のではなく、「何か起きる前から状態を把握し、予防する」という発想が、安定運用には不可欠です。
6-2. トラブル事例とその対応(通信遮断・ルーティング不整合・VLAN隔離失敗)
どれだけ丁寧に設計・監視していても、L3スイッチを運用しているとトラブルは必ず起こります。
そこで重要なのが、「よくあるトラブルパターン」を知っておき、対応の流れをあらかじめイメージしておくことです。
ここでは、L3スイッチに関する代表的なトラブルとして、
- 通信遮断
- ルーティング不整合
- VLAN隔離失敗
の三つを取り上げ、それぞれの原因と対応を整理します。
6-2-1. 通信遮断のトラブル(リンクダウン・STP・ACL誤設定)
まずは、「突然ある区画だけ通信できなくなった」「特定の経路がまったく通らない」といった、通信遮断系のトラブルです。
代表的な原因の例:
- 物理リンクの断(ケーブル断線、SFPモジュール故障など)
- STP(スパニングツリープロトコル)のブロックポート変化
- ACLの誤設定による通信遮断
- ポートシャットダウンの誤操作
このようなとき、L3スイッチのトラブルシュートの流れは、次のように進めると効率的です。
- どの範囲で通信できないかを特定する
- 端末同士なのか、VLAN間なのか、インターネットだけなのか
- L3スイッチのインタフェース状態を確認
- 該当ポートがリンクアップしているか
- エラー/Discardが急増していないか
- STPやルーティングの状態を確認
- ループ防止のためのポートが意図せずブロックされていないか
- 経路が別ルートに切り替わっていないか
- ACLやフィルタ設定を確認
- 最近の設定変更がないか
- 関連セグメントの通信をdenyしていないか
- 最近の変更履歴・作業記録を見返す
- 直近の設定変更が原因であることが多い
つまり、L3スイッチで通信が止まったときは、「物理 → L2 → L3 → ACL → 変更履歴」の順で切り分けると、原因にたどり着きやすくなります。
6-2-2. ルーティング不整合のトラブル(スタティック/OSPF)
次に多いのが、L3スイッチのルーティング不整合によるトラブルです。
例えば、「片方向だけ通信できる」「一部のネットワークにだけ到達できない」といった症状が典型です。
原因の例:
- スタティックルートの設定ミス(宛先ネットワークやネクストホップ誤り)
- デフォルトルートの競合や消失
- OSPFなどダイナミックルーティングの設定不整合
- ネイバー不成立
- エリア設定の不一致
- フィルタリングによる経路の落ち
- 非対称ルーティング(行きと帰りの経路が違う)
このようなルーティング系トラブルの対応は、次のステップで切り分けると分かりやすくなります。
- ルーティングテーブル(show route など)の確認
- 宛先ネットワークへのルートがL3スイッチ上に存在するか
- 経路の優先順位(メトリック・AD)が期待通りか
- ネクストホップへの到達性確認
- L3スイッチからネクストホップIPへpingが通るか
- 経路交換の状態確認
- OSPFや他プロトコルのネイバー状態(establishedかどうか)
- 経路再配布の設定有無
- 片方向通信の有無を確認
- A→Bだけ通らないのか、B→Aも通らないのか
- 片方向だけ通らない場合、戻りルートが存在しないケースが多い
つまり、「ルーティングテーブルにない経路は通らない」「ネクストホップに届かなければその先にも届かない」という基本に立ち返り、L3スイッチ上で経路がどう見えているかを丁寧に確認することが重要です。
6-2-3. VLAN隔離失敗のトラブル(タグ設定・ポート種別ミス)
最後に、「本来分離すべきVLAN間で通信できてしまった」「逆に、同じVLANのはずなのに通信できない」といった、VLAN関連のトラブルです。
これは、L3スイッチをVLAN間ルーティングに使っている環境で特によく起こります。
主な原因の例:
- アクセスポートとトランクポートの設定ミス
- VLANタグ(IEEE 802.1Q)の設定不一致
- 未使用VLANが意図せずトランクに通されている
- L3スイッチ側のSVI設定ミス(間違ったVLANとIP紐付け)
- ACL未設定/誤設定で、遮断すべきVLAN間通信が通ってしまう
VLANトラブルの切り分けでは、次の観点を順に確認していくと整理しやすくなります。
- 端末のVLAN認識
- 接続ポートが本当に想定のVLANに所属しているか
- ポートのmode(access/trunk)とPVIDが正しいか
- スイッチ間リンク
- トランクポートで通すVLANの許可リスト(allowed VLAN)が正しいか
- タグあり/なし(tagged/untagged)の設定が左右で一致しているか
- L3スイッチのSVI設定
- 各VLANのIPアドレスとサブネットマスクは正しいか
- 不要なSVIが残っていないか
- ACL・ポリシー
- 本来遮断すべきVLAN間通信に対して、明示的なdenyが入っているか
- 「any any permit」のような広すぎるルールがないか
その結果、「L3スイッチのVLAN設定が正しいか」「周辺のL2スイッチとの組み合わせで不整合がないか」を一つひとつ潰していくことが、VLANトラブル解決の近道になります。

IT資格を取りたいけど、何から始めたらいいか分からない方へ
「この講座を使えば、合格に一気に近づけます。」
- 出題傾向に絞ったカリキュラム
- 講師に質問できて、挫折しない
- 学びながら就職サポートも受けられる
独学よりも、確実で早い。
まずは無料で相談してみませんか?