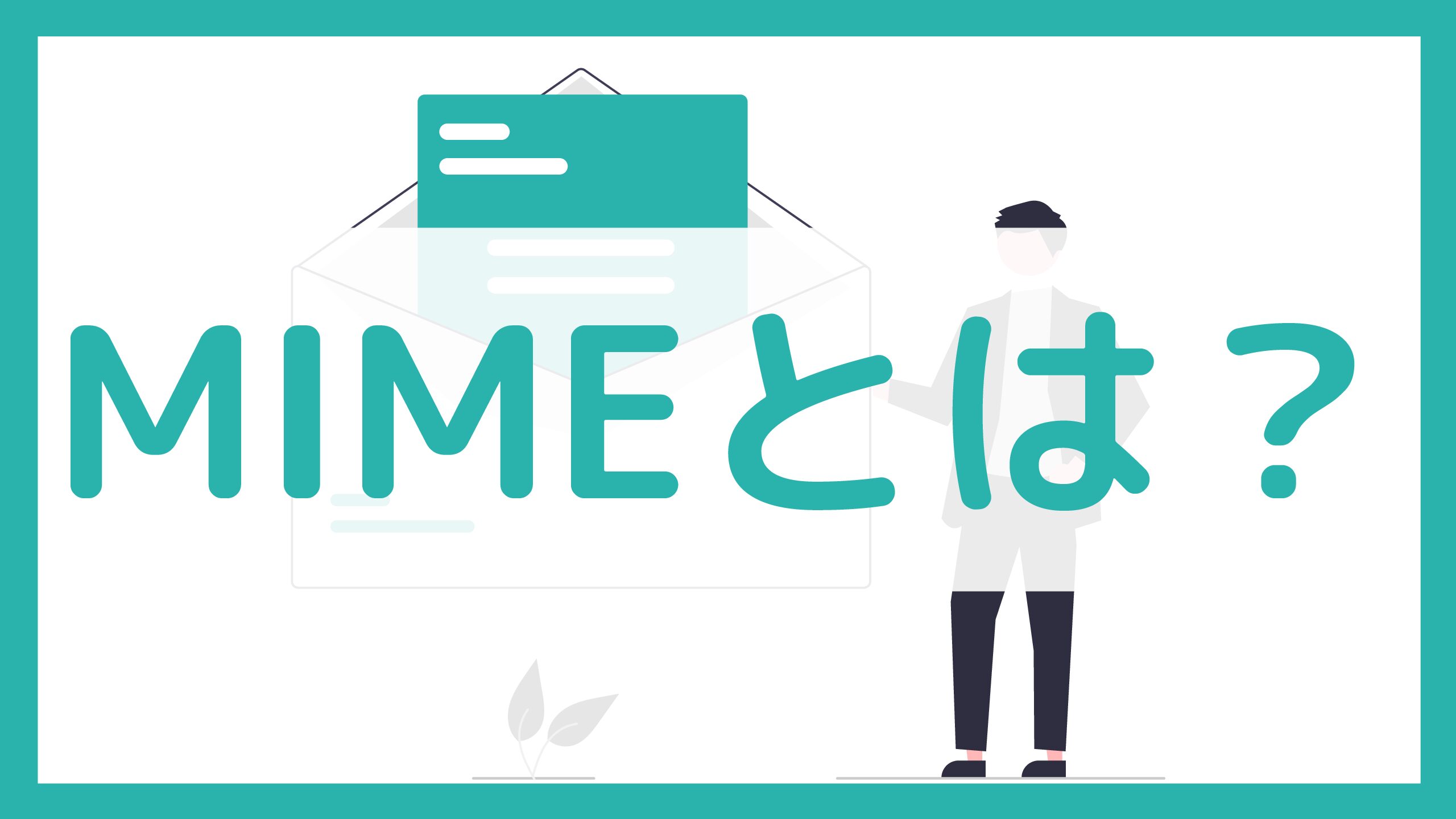近年、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる中、「セキュリティ規格」に注目が集まっています。
しかし、どの規格を選ぶべきか、取得には何が必要なのか、具体的な手順や費用が分からず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな悩みを解消するために、主要なセキュリティ規格の種類から導入手順、最新動向までをわかりやすく解説します。
企業の信頼性を高める第一歩として、ぜひご活用ください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- セキュリティ規格とは何か知りたい人
- どのようなセキュリティ規格があるのか知りたい
- 最適なセキュリティ規格がどれか分からない
セキュリティ規格の基礎知識
現代のデジタル社会において、企業や個人が扱う情報の重要性はますます高まっています。そんな中で「セキュリティ規格」は、情報の安全を守るために欠かせない存在です。
この章では、「セキュリティ規格とは何か」「なぜ重要なのか」をわかりやすく解説していきます。
1-1. セキュリティ規格とは
セキュリティ規格とは、情報の機密性・完全性・可用性を確保するために定められたルールや基準のことです。これらの規格は、企業や組織が情報を安全に管理し、外部からの脅威に対抗するためのガイドラインとして機能します。
例えば、「ISO/IEC 27001」は最も広く知られているセキュリティ規格のひとつで、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の構築・運用・改善のための国際標準です。
1-1-1. 主なセキュリティ規格の例
| 規格名 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 27001 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) | 企業全体 |
| ISO/IEC 15408(CC) | 情報システムのセキュリティ評価基準 | ソフトウェア・ハードウェア製品 |
| ISO/IEC 27017 | クラウドサービスにおけるセキュリティ管理 | クラウド利用者・提供者 |
このように、セキュリティ規格には対象や目的に応じてさまざまな種類があります。
1-2. セキュリティ規格の重要性
セキュリティ規格が重要とされる最大の理由は、組織や個人の情報資産を守るための「信頼の基盤」を築ける点にあります。つまり、セキュリティ規格の遵守は、対外的な信頼を獲得し、ビジネスを継続するうえでの「安心材料」となるのです。
1-2-1. セキュリティ規格が重要な理由
- 情報漏洩の防止:内部不正やサイバー攻撃からの保護
- 顧客・取引先の信頼確保:セキュリティ対策を実施している証明として活用
- 法令遵守(コンプライアンス):個人情報保護法やGDPRなど、法的要求事項への対応
- 業務効率の向上:標準化された手順により業務の無駄を削減
したがって、セキュリティ規格を導入することは、単なる「守り」だけではなく、組織の競争力を高める「攻め」の一手でもあるのです。
主なセキュリティ規格の種類
セキュリティ規格にはさまざまな種類があり、用途や対象に応じて選ぶ必要があります。
本章では、代表的なセキュリティ規格を取り上げ、それぞれの特徴や適用範囲について解説します。どの規格を導入すべきか悩んでいる方にとって、選定の手助けとなる内容です。
2-1. ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)
「ISO/IEC 27001」は、情報セキュリティに関する国際的な標準規格であり、最も広く利用されているセキュリティ規格の一つです。
2-1-1. ISO/IEC 27001の特徴
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を構築・運用・改善するための指針
- 組織全体での情報リスクの識別・管理が可能
- 対外的な信頼を得やすく、取引条件にされることもある
つまり、ISO/IEC 27001は「企業のセキュリティ対策の骨格を形成する」重要な規格です。
2-2. ISO/IEC 15408(共通評価基準:Common Criteria)
ISO/IEC 15408は、製品のセキュリティ機能を評価するための国際基準です。特に、IT製品やシステムの安全性を第三者が評価・認証する際に用いられます。
2-2-1. ISO/IEC 15408の特徴
- 製品やシステムが持つセキュリティ機能の評価基準
- 政府機関や大規模システム向けに導入されやすい
- 海外での製品展開にも有利になる場合がある
したがって、情報システムやセキュリティ製品を開発・提供する企業には重要なセキュリティ規格です。
2-3. ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ)
クラウドの利用が増える中で注目されているのが、ISO/IEC 27017です。このセキュリティ規格は、クラウドサービスにおけるリスクに特化して策定されています。
2-3-1. ISO/IEC 27017の特徴
- クラウド環境特有のセキュリティリスクへの対策を明示
- クラウドサービス提供者・利用者の両方に適用可能
- ISO/IEC 27001の拡張として位置づけられている
つまり、クラウドベースのサービスを利用する企業には、導入価値の高いセキュリティ規格です。
2-4. ISO/IEC 27701(プライバシー情報マネジメント)
ISO/IEC 27701は、個人情報の管理に特化したセキュリティ規格で、プライバシー保護の観点から注目されています。
2-4-1. ISO/IEC 27701の特徴
- ISO/IEC 27001にプライバシー要件を追加した拡張規格
- GDPR(EU一般データ保護規則)などの法令対応に有効
- 個人情報を扱うすべての組織が対象
なぜなら、個人情報保護の重要性が高まっている現在、この規格の取得は企業の社会的信頼を向上させる手段にもなるからです。
2-5. その他の関連規格
上記以外にも、特定の業界や用途に対応したさまざまなセキュリティ規格があります。
2-5-1. その他の主なセキュリティ規格
- NIST SP 800シリーズ(アメリカ国立標準技術研究所のセキュリティガイドライン)
- PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)
- SOC 2(サービス組織向けのセキュリティ・可用性評価)
それぞれの規格には独自の目的と適用範囲があるため、自社の業務内容やリスク環境に応じて適切な規格を選ぶことが重要です。
セキュリティ規格導入のメリット
セキュリティ規格を導入することは、単に外部からのサイバー攻撃を防ぐだけではありません。組織全体の運営基盤を強化し、信頼を高め、法令に対応するための「戦略的な投資」と言えるのです。
この章では、セキュリティ規格の導入によって得られる具体的なメリットを詳しく解説します。
3-1. 情報リスクの低減
最も直接的な効果は「情報リスクの低減」です。セキュリティ規格には、リスクを特定し、評価し、管理するための明確なプロセスが定められています。
3-1-1. なぜリスクが減るのか?
- 脅威に対する対策が体系的に整備される
- 定期的なリスク評価により、脆弱性を早期発見できる
- 事故発生時の対応手順(インシデント対応)も明文化されている
つまり、セキュリティ規格の導入は「想定外のリスク」を減らし、組織の耐久力を高めるための有効な手段です。
3-2. 組織の信頼性向上
セキュリティ対策が明文化され、第三者認証を受けていることは、取引先や顧客からの信頼獲得につながります。
3-2-1. 社外からの評価が変わる理由
- 認証取得がビジネスの差別化要因になる
- 大手企業や官公庁との取引要件として重視されることもある
- 社内外へのセキュリティ意識の向上にもつながる
その結果、セキュリティ規格を導入した企業は「安全性の高い信頼できる組織」として評価されやすくなります。
3-3. 法令遵守の推進
現代では、個人情報保護法やGDPRなど、情報セキュリティに関する法令やガイドラインが世界的に厳格化されています。セキュリティ規格は、こうした法的要件への対応を支援します。
3-3-1. セキュリティ規格と法令の関係
- 各種セキュリティ規格は、法令に準拠した運用の指針として利用可能
- 内部統制の強化につながるため、監査対応も容易になる
- 海外展開を視野に入れる企業には特に重要
従って、法令遵守を継続的に実現するためにも、セキュリティ規格の導入は欠かせません。
セキュリティ規格取得の手順
セキュリティ規格を取得することは、情報セキュリティの体制を可視化し、外部からの信頼を高めるための有効な手段です。
しかし、取得には一定のプロセスと準備が必要です。
この章では、セキュリティ規格を取得するための具体的なステップを順を追って解説します。
初めての方でも迷わず進められるように構成しています。
4-1. 現状分析とギャップ分析
最初のステップは、自社のセキュリティ体制の現状を正しく把握することです。
4-1-1. ギャップ分析とは?
ギャップ分析とは、「現在のセキュリティ対策」と「目標とするセキュリティ規格の要件」の差を明らかにする工程です。
- 自社の情報資産、リスク、既存の対策を洗い出す
- セキュリティ規格の要求事項と照らし合わせて、不足点を明確化
- 優先順位をつけて対応計画を策定
つまり、ここでの分析が正確であればあるほど、後工程のスムーズな進行が期待できます。
4-2. ISMSの構築
次に行うのが、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の構築です。
これは特に「ISO/IEC 27001」取得を目指す際の中心的な取り組みです。
4-2-1. ISMS構築の主なステップ
- 情報セキュリティポリシーの策定
- リスクアセスメント(脅威・脆弱性の洗い出し)
- 管理策の選定(技術的・組織的対策)
- 運用手順の文書化と従業員教育
従って、ISMSの構築は「セキュリティ規格の要件を実際の運用へと落とし込む」重要なフェーズとなります。
4-3. 内部監査とマネジメントレビュー
構築したISMSが適切に機能しているかを確認するために、内部監査とマネジメントレビューを実施します。
4-3-1. 内部監査の目的
- ISMSがセキュリティ規格に適合しているかを自社でチェック
- 文書や記録を通じて証跡を確認
- 改善すべき点を洗い出し、是正処置を実施
4-3-2. マネジメントレビューの意義
- 経営層がISMSの有効性を評価
- リスクの変化や外部環境の変化を踏まえた方針見直し
- 改善計画の決定
したがって、このステップは「継続的改善(PDCA)」の中心となるフェーズです。
4-4. 認証取得と維持
最後に、第三者機関による審査を経て、正式な「セキュリティ規格認証」が発行されます。
4-4-1. 認証取得の流れ
- 認証機関との契約・日程調整
- 第一次審査(文書審査)
- 第二次審査(現場審査)
- 指摘事項の是正と認証取得
4-4-2. 維持のためのポイント
- 毎年のサーベイランス審査(維持審査)への対応
- 定期的な内部監査・教育の実施
- 継続的な改善活動の記録
だからこそ、取得後も「セキュリティ規格は常に運用し、更新し続けるもの」であることを意識する必要があります。
最新のセキュリティ規格動向
テクノロジーが進化し続ける中、セキュリティに関する脅威も高度化・多様化しています。それに伴い、セキュリティ規格も時代に合わせて進化しています。
この章では、特に注目すべき最新のセキュリティ規格の動向を2つのトピックに分けて紹介します。
5-1. 政府機関等のサイバーセキュリティ対策の統一基準群
2020年代に入り、日本政府はサイバー攻撃に対する防御力を高めるために、セキュリティ規格やガイドラインの標準化を強化しています。
5-1-1. 統一基準群とは?
統一基準群とは、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が策定した、政府機関および重要インフラ事業者向けのサイバーセキュリティ対策基準です。
主な特徴:
- 各省庁・組織間でばらつきのあった対策を統一
- 国際的なセキュリティ規格(ISO/IEC 27001など)と整合性のある構成
- ガイドライン・手引書の形で提供されており、企業も参考にできる
つまり、政府主導のセキュリティ規格の方向性を知ることで、民間企業においても対策のレベルアップが可能になります。
5-2. IoT機器に関するセキュリティ標準規格の進化
スマートホームや自動運転車など、IoT機器の普及に伴い、新たなセキュリティリスクが生まれています。
これに対応するため、IoT機器向けのセキュリティ規格も整備が進んでいます。
5-2-1. 代表的なIoT向けセキュリティ規格
| 規格名 | 概要 |
|---|---|
| ETSI EN 303 645 | 欧州で策定された消費者向けIoT機器のセキュリティ基準 |
| ISO/IEC 27400 | IoTのセキュリティリスクと対策の枠組みを定義 |
これらの規格は、メーカーがセキュリティ設計を製品段階から組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」を促進します。
したがって、今後の製品開発やサービス展開においては、これらの最新セキュリティ規格への準拠が差別化のポイントとなるでしょう。
セキュリティ規格に関するよくある質問
セキュリティ規格に興味を持っても、「導入にどれくらい時間がかかるの?」「費用は高いの?」といった疑問を持つ方は多いです。
この章では、特に多く寄せられる質問とその回答を取り上げます。
6-1. セキュリティ規格の取得にどれくらいの期間と費用がかかるのか
セキュリティ規格の取得には、準備から審査、取得後の運用までを含めて一定の時間とコストがかかります。
ただし、組織の規模や準備状況によって大きく異なります。
6-1-1. 一般的な取得期間と費用の目安
| 項目 | 中小企業の目安 | 大企業の目安 |
|---|---|---|
| 取得期間 | 約6〜12ヶ月 | 12ヶ月以上 |
| 初期費用 | 数十万円〜100万円前後 | 数百万円〜 |
| 維持費用(年) | 数十万円程度 | 数百万円程度 |
ポイント:
- 自社で対応するか、コンサル会社を使うかで費用は変動
- 取得のための準備期間に、教育や社内体制の整備も含まれる
だからこそ、計画的に進めることが重要です。また、長期的に見れば、セキュリティ事故のリスクを減らすことで、結果的にコスト削減にもつながります。

IT資格を取りたいけど、何から始めたらいいか分からない方へ
「この講座を使えば、合格に一気に近づけます。」
- 出題傾向に絞ったカリキュラム
- 講師に質問できて、挫折しない
- 学びながら就職サポートも受けられる
独学よりも、確実で早い。
まずは無料で相談してみませんか?